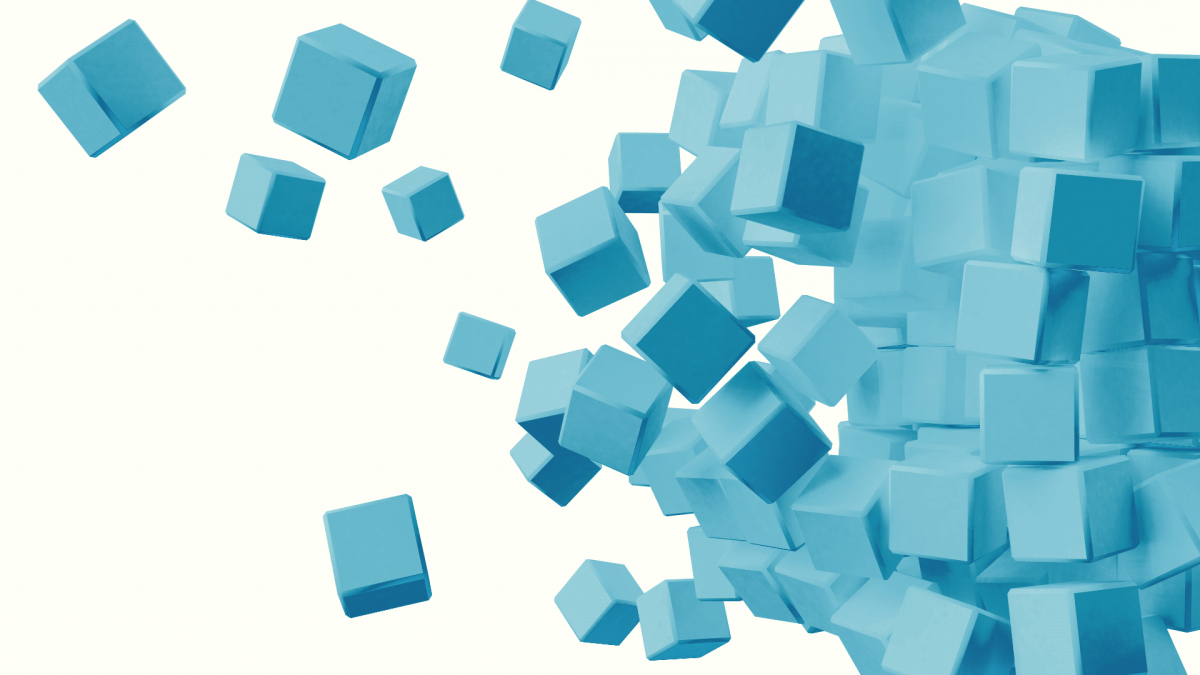どこかのいつかの女の子の話
帰ってきたらただでさえ少なかった母親の荷物がまるっとなくなっていて、あ、逃げたんだ、と察すると同時に、お母さんやるなあと思った。
私もなんかした方がいいかな~とぼんやり考えているうちに父親が帰ってきたので、いつものようにコソコソと台所のすみに逃げた。
ゴンゴン、ビチャビチャと大きい動作でお酒を作るいつもの音が響いたあとは、テレビの音だけが流れる。お母さんがいなくなったの気付いてないのかな。荷物もないんだけど。でもいつもお母さんと私の二人はお父さんの目に止まらないようにコソコソ過ごしてたから、お父さんにとってはいつも通りなのかもしれない。
居間からこぼれる光でどうにか本を読もうとしているところで「おい!飯は!」と怒声が聞こえてきた。このままだとまずいと分かっているのでササッと玄関から外へ出る。
「おい! いねえじゃねえか! 俺の飯どうするつもりなんだ! どこ行きやがった! おい!!」
どたんばたんがちゃんばりん。
暴れている音を聞きながら、早く収まってほしいけど今日は駄目かもなと思う。アパートの裏手に回って、いつからあるのだか誰のものだかもさっぱり知らないボロボロの椅子に腰かける。学校指定のコートと100円均一で買ったペラペラのブランケットでどうにか丸くなった。早く収まってほしい。
学校の休み時間に「家出したいからちょっと泊めてよ」「いいよ、ママに話してみる」なんてクラスメイトが話していたのを思い出す。普通の子はこういうとき誰か友達の家に行ったりするのかな。小学校に上がってからはずっと『あの家の子とは遊んじゃいけません』指定を食らっていたから、私はすっかり友達の作り方なんて忘れてしまった。もちろん泊まれる当てなんてない。
お母さんには、当てがあったのかな。私も連れてってほしかった、とちらりと思ったけど、私だって逃げられるチャンスがあったらお母さんを置いてでも逃げただろうなあと思うので、お互い様だった。
お母さんがいなくなっても食事の心配ばかりしている父親を冷ややかに見ていた私だったけれど、翌日からは私も同じく食事の心配ばかりする羽目になった。たしかにお父さんが私になにか用意してくれたことなんてないからそりゃこうなるよね。給食があってよかったなと心の底から思った。給食のときの私はまるで餓鬼みたいな有様だけど、最初から友達なんていないのであまり気にしない。そんなことより数少ない食事の機会を逃す方が大変だ。
そんな幸せな給食も土日には逆さに振ったって出てこない。私はあまり父親と顔を会わせたくないから普段は台所のすみの納戸に引きこもりがちになっていた。それでもお母さんがいなくなったからにはもう自分でどうにかするしかなくなってしまって、掃除をするふりをしながら必死になって父親が酔ってまき散らした荷物から小銭を探すのが日課になった。意外と10円玉や5円玉はちゃりちゃり見つかるので、音を立てて見つかってしまわないようにできるだけしっかり隠す。
セールの食パンと板チョコがもっぱら私の購入品だ。主食を食べてるとちゃんとしてるなという気がするし、山で遭難していた人もチョコレートを食べて生き延びたと教科書のコラムで読んだから、きっとチョコは体にいい。よく分からないけど。板チョコは日持ちがするしひとかけらずつ食べれば何日も楽しめる私のお気に入りだった。
そんな風にギリギリどうにか飢えない生活をしていたけど、飢えなければそれでいいというものでもない。今はまだ家に置いてある分でなんとかなっているものの、掃除道具や洗剤、学校で使う文房具だっていつかはなくなってしまう。ご飯ばかり買ってるわけにもいかないよなー、でもお金なんてどうやって調達したらいいんだろ、とウロウロ自販機の小銭を探していたら、パチンコ屋の近くで知らない女の人と歩いている父親を見つけてしまった。
大人、大人って、えー。私はお母さんがいなくなったら生きるのにもギリギリなのに大人はそうじゃないんだな。お父さんはコンビニに行けばご飯を食べられるし、昼間はパチンコに行って知らない女の人とデートもできるし、夜に家で飲むお酒だって買ってこられるのだ。あーあ。
その日は夜になっても父親が帰ってこなかった。もしかしたらパチンコが長引いているか、飲みに行っているか、それともあの女の人とどこかへ出かけているのかもしれない。珍しいけれど今までまったくなかったわけではない。滅多にないチャンス、でももしかしたら帰ってくるかも、と油断しないようにと思う反面どうにもそわそわしながら父親が放置していた缶詰なんか温めちゃおうかなと考えたところで、玄関からすごい音がして私は飛び上がった。
「**さ~~~~ん、いるんでしょお~~~~~~!?!? 電気ついてますもんねえ~~~~~~!!!! 先週この日まで待ってくれたらちょっとでも返しますってあなたが言った日からもう三日も過ぎてるんですよお~~~~~~!!!! ねえ**さ~~~~ん!!!!」
ドンドンドンドン!!!!
大きい音に固まってしまっていた私だったけれど言われている間にピンときた。お父さんの借金、お母さんがいなくなったから誰も払ってなかったんだ!!
「もう利子えらいことになってんですよお~~~~~~!!!! **さんちゃんと返せるんですかあ~~~~~~!?!? 今日ちょっとでも出してもらった方がお互いに助かると思うんですけどねえ~~~~~~!!!!」
うろたえてるばかりで無反応の室内にいらだったのか、乱暴なノックがドアを蹴る音に変わっていよいよ玄関は騒々しくなる。ゴンゴンゴンゴン!!!!
「オイ中にいるんだろが!!!! 電気ついてんのバレバレなんだよ!!!! 利子だけでも今日出さなきゃぜってえ帰らねえかんな!!!! オメエ嫁子どもがいんだろ!!!! そいつら売っぱらって払ってもらってもいいんだぞこっちゃよお!!!!」
勢いよく開いた扉に外の人物は驚いたようだった。「おわっ! てめ、」若い男の人だ。黒いシャツにだらんと下がったネクタイ。ギラついた目が私を睨み付けようとして、黙った。小娘が出てくるとは思っていなかったのかもしれない。
「売れますか」
「あ?」
「私、あの、娘ですけど、売れますか」
男の目が室内を遠慮なくじろじろ観察する。小銭があったらすぐ拾えるようにできるだけ綺麗にしているつもりだけど、なんとなく恥ずかしい。
「……親父は? それか母ちゃん」
「お母さんは、何週間か前にどこかへ行きました。お父さんは、パチンコか居酒屋か、分かりません」
「飯は食ってんのか」
「食べてます、食パン。あの、お金、小銭しかなくて返せないので、私、売れますか?」
最初の質問をもう一度繰り返す。今度は私を上から下までじろじろ見たあと、男の人ははーっと息を吐いて「ついてこい」とぶっきらぼうに言った。
後部座席で揺られている間ずっとドキドキしていた。どんなところに売られるとしても父親よりまともな人間がいればいいと思ってはいるけれど、脳裏によぎるのはセクシーなスーツに身を包んだ無表情のお姉さんか、黒張りの椅子にでっぷり腰かけた人相の悪いおじさんだ。そんな人が出てきてもビビらないようにしないと。
「降りろ」
ぎゅうぎゅうに制服のスカートを握りしめた私が連れてこられたのは、思ったよりも普通の雑居ビルだった。男の人はずんずん進んでいくので、遅れないよう頑張ってついていく。
「兄貴は?」
「今いる。奥の部屋」
「兄貴。すいません、シマです。入ります」
男の人と似たり寄ったりの怖そうな人たちの間をおっかなびっくり通り抜けて、奥の扉を見つめる。「おう入れ」入室を促す声に、ビビらないようにともう一度背筋を伸ばして、現れたのは果たして私の想像とは全然違う人だった。
うすく銀に光る白い髪。鋭い赤い目。どう控え目に言ってもクラスで人気のイケメンが足元にも及ばない顔。不機嫌そうにひそめられた眉もそれらを引き立てるために思えてくる。この世で一番美しい生き物ですと言われたら頷いてしまいそうな造形美だったけれど、身にまとう雰囲気は間違いなく怖そうなお兄さんたちを束ねる人物だという恐ろしさがあった。
「すいません兄貴、本命はいませんでした。嫁さんも一ヵ月くらい前に飛んじまったらしくて、ろくに飯も食ってないガキが放置されてるだけで」
「あぁ?」
兄貴さんの目が私に向けられる。怖い。でもこの人に売られるんだとしたら、変なところは見せられない。
「……お前、食えないもんあるか。アレルギーとか」
「ないです。なんでも食べます。この前カビたパン食べても大丈夫でした」
兄貴さんの眉がいっそう険しくひそめられた。なんでも食べられるのはいいことだと思っていたけれどそうではなかったのかもしれない。さっきの自分の発言を今すぐ引っ込めたくなって、耳の後ろが熱くなった。
「あの、ダメですか。安くなりますか?」
「あ?」
「私、本当にお金を持っていなくて、できるだけ高く売れた方が多分助かるんです」
「あー……」
兄貴さんがタバコの箱に手を伸ばして、手の中で遊ばせる。火を付ける気配は無い。ここまで連れてきてくれた男の人がビッと身を固くした。
「ガキに余計なこと聞かせんな」
「す、すいません」
一万円札が尻ポケットに入っていた財布から取り出される。一万円札。私、初めて見たかもしれない。
「今いる奴らに本命探させろ。お前は弁当と飲み物、適当に買ってこい」
「電話してくるからゆっくりしてろ」と兄貴さんは出ていってしまったけれど、とてもじゃないけどゆっくりなんてできるはずもなく、高そうなソファにできるだけ浅く腰かけて縮こまっている。時間の感覚もまるで分からなくなって、誰か見とがめられるんじゃないかとビクビクしながら目線だけで壁にかけられている時計を確認したら、ここにきてせいぜい10分程度しか経っていなかった。嘘でしょ。
息さえも苦しくなってしまったような気がして、どうにかがんばって心臓の音を落ち着かせようとしているうちに最初の男の人が帰ってきた。
「ただいま帰りました! ……あれ、兄貴は?」
「で、電話だって」
「おー」
自分で聞いたくせにあんまり興味なさそうに答えて、男の人はスーパーの袋から中身をずんずんとテーブルへ並べていく。弁当が五個ばかりと、お茶や炭酸のジュースのペットボトルが何本か。並べられるのを凝視するみたいに固まってしまっていたけれど、手伝った方がよかったかもと後悔した。
「なんか好きなもん選べよ。全部食ってもいいし、余ったら俺らで食うから」
そんなこと言われても。この状況で喉を通るとは思えない。どうしたらいいのか分からなくておろおろと目線をさまよわせていると、「はよしろや。お前が食ってないと俺が兄貴になに言われっか分かんねえ」とせっつかれた。ひえ。もう一度ざっと見て、下から二番目の値段の弁当とウーロン茶を手に取った。チキンタルタル弁当。
いただきますと手を合わせてからもそもそ弁当を食べる。給食以外でこんなにちゃんとしたものを食べるのは久しぶりのはずだけれど、状況のせいで味なんてちっとも分からなかった。それでも私を監視するみたいな男の人の目が恐ろしくて、箸を止めないように、でもゆっくりと口に物を運び続けた。
「あ、兄貴おかえりなさい!」
男の人の声に一瞬で背筋が伸びる。口に入れていたものが気管の方に入りそうになって、慌ててウーロン茶で流し込んだ。
「おう。……お、食ってんな。美味いか?」
「あ、はい。ありがとう、ございます」
兄貴さんが向かいのソファに腰かける。今まで気にしていなかった自分の仕草が急に恥ずかしくなってくる。人生で一番きれいに見えるように頑張って、いよいよ口に入れてるものが何かさえ分からなくなってきた。弁当はまだ四分の一くらい残っている。
「……母ちゃんいなくなって寂しいな」
私じゃない人に話しかけているみたいな言葉だった。それでも体中の血が一機に熱くなったような気がした。
「あの! 違うんです! お母さんはいいんです! 寂しくないんです! よかったんです!」
兄貴さんの顔が不機嫌そうにゆがむ。怖い。それなのに私はまくしたてるのを止められなかった。
「お母さんは私と違ってお父さんに叩かれてたから、逃げてよかったんです、もう叩かれなくていいんです。お母さんは悪くなかったのに、だから、寂しいとかじゃなくて、もう叩かれなくてよくて、お母さんはこのままでいいんです。よかったんです」
言っているうちにどんどん感情が昂ってきて、涙がぼろぼろと溢れてきた。
私とお母さんは、親子というより、お父さんという災厄を二人で乗り越える仲間みたいなものだった。私よりつらい目に合っているのに私を守り、励ましてくれる存在。母親なら当然と思われるかもしれないけれど、お父さんという災厄があまりにも身近にあったから、いつも二人で励ましあって寄り添って、私はなんだか年の離れたお姉さんみたいに思っていたのだ。
だから、お母さんが逃げられたことは、私にとって本当に嬉しいことだった。もう少し気安い関係だったら「よかったね!! おめでとう!! 落ち着いたらどうやったのか話して聞かせてよ!!」とクラスの女子たちみたいにはしゃいで喜びを伝えたかったくらいだ。ようやく逃げ切れた仲間の足を引っ張りたくはない。絶対に。
「お母さんは、いいんです。これでいいから、お母さんのこと探したりしないでください。放っておいてあげてください。お金が必要なら私を売ります。私がお金を返します。お父さんのところにいるよりはずっといいです。だから、お母さんのことは、お母さんは」
とうとう涙が嗚咽になって、もう言葉にならなかった。またまずいことを言ってしまっただろうな。安くなってしまうかもしれない。自分の冷静な部分はそう考えるけど、一度熱くなってしまった涙腺はなかなか冷めてはくれない。
ひどい顔を伏せてべそをかいていると、不意に真っ白なタオルが投げてよこされた。
「悪かった。……おら顔拭け」
今まで見た中で一番ふかふかで真っ白で高級そうなそれに一瞬ためらったけど、そのまま目元に持っていった。泣きっぱなしでいるよりはいいはずだと思う。
「お前がそんなに言うなら母ちゃんは探さねえ。そのままにしておく。約束だ」
身を乗り出した兄貴さんが私の頭を撫でる。意外とやわらかい手つきだった。優しいと言っていい。男の人にこんな風に頭を撫でられるのは、きっと初めてだった。
「兄貴、入間さんが来られました」
いつの間にか部屋を出ていた男の人がドアの影から告げる。顔を上げようとしたけれどまだ涙が止まらなくて、ぐっと堪えた。
「左馬刻、お前いきなりこんなことなァ」
「おーこえこえ。こんなとこにガキを置いとくつもりかよ、薄情なウサちゃんだなァ?」
「っ、てめ」
私がひいっと終わらせられなかった嗚咽を漏らしたことで全員黙った。気まずい。
「あなたが**さんですか? もう大丈夫ですからね」
新しくきた眼鏡の人が私に優しく話しかける。どうしたらいいのか分からなくて、曖昧に会釈を返した。
「コイツがお前を買いに来たヤツだ。せいぜい幸せに暮らせよ」
兄貴さんがポンポンと私の頭を叩いた。それがあんまり優しい気がして、これからのことも分からないくせに私はただその感触を覚えることに必死になった。
眼鏡の人も、兄貴さんに負けず劣らず綺麗な顔をしていた。こんな人が私みたいな人間を買うなんて世の中不思議だなと思っていたら、「準備が整うまでここで待っていてください。不自由があればこの方に」と見知らぬおばさんが時折うろつくアパートの一室のような場所に押し付けられて、ああここは人買いの商品を入れるための場所なんだ、あの人はそういう仲介をしているんだと思ってビクビク怯えて縮こまって過ごした。
二日ばかり経つと若いお姉さんがやってきて私を連れだした。今度こそ私を買う人のところへ連れていかれるのだとばかり思っていたのに、たどり着いたところは児童養護施設だったので、私は口を大きく開けてなにも言えなくなるくらい驚いた。戦災孤児が多いというその施設の職員さんが温かく迎えてくれて、「お父さん、早く見つかるといいね」と背中をさすってくれたところで父親がどうも行方不明ということになっているらしいことを知り、さらに驚いた。
そうして始まった私の施設での暮らしは、わいわいぎゃいぎゃいと四六時中誰かが騒いでいてやかましいけれど、三食つつがなく食べられるし、お風呂も毎日入ることができるし、なんと望めば高校にだって進むことができるらしく、とにもかくにも恵まれていた。
施設で過ごす中であの眼鏡の人が人買いどころかなんと警察の人だったということも知って驚いた。半年ほど経って、視察という名目で本人がやってきたときにどうにかお礼を言うことに成功した。
「刑事さん、あの、私を連れだしてくれてありがとうございました」
「私は刑事ではないですよ。警察官ではありますが。それに、お礼を言われることの程ではありません。職務ですから」
一度、望むならばお母さんと連絡がとれると教えてもらったこともある。それでも、あのとき私たちは確かに仲間だったけれど、そのあとの生活を邪魔したくはなかったので首を横に振った。ただどうか幸せであってほしいと思った。
それまでの私を知らない人が見ればまるで生まれたときからそうだったみたいに普通の幸せを得ることができた。すべてを知っている私からすると、まるで驚きの連続だったのだけれど。一番驚いたのはあのとき私を助けると決めた白い髪の兄貴さんがハマのキングとも呼ばれた碧棺左馬刻その人であったというところなのだが、私がそれを知って腰を抜かすくらい驚くのは、施設に入ってから何年も後のことだ。
2020/02/08 初公開