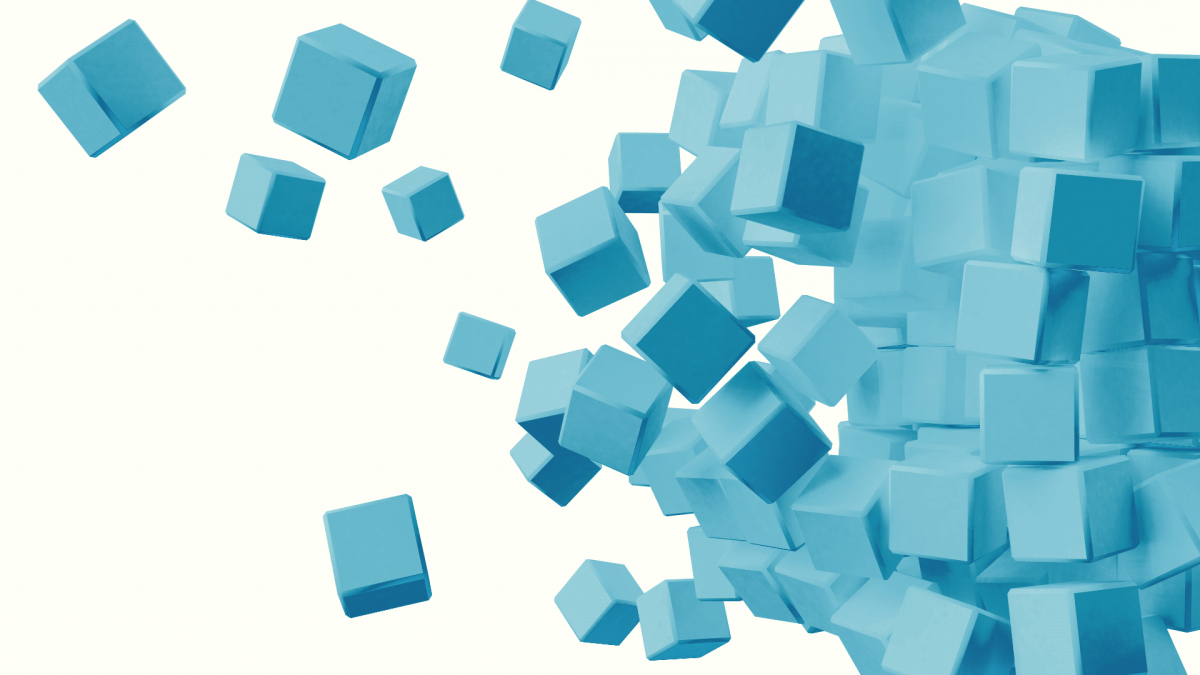夢野に誕生日を祝ってもらう話
最初の誕生日は、たしかマッサージオイルとボディクリームのセットをいただいた。
クリスマスには憧れのブランドのコフレ、お気に入りの店のお菓子つめあわせ、海外有名店のチョコレート、店先であれいいねなんて話した入浴剤。夢野幻太郎という人は、ことあるごとに私に贈り物をくれる。編集さんからの差し入れのお裾分けなんかを含めると、もはや思い出すこともできないくらいの量だ。
そういったものを貰うたびに、熱にのぼせている私は愛されているなあと嬉しくなってしまうのだけど、あるときにハッと気が付いた。食べたり使ったりしたらなくなってしまう、いわゆる消えものしか彼はプレゼントしないのだ。
今までの贈り物が不満なわけじゃない。特別形に残るものを欲しいとねだって困らせたいわけでもない。だから私はこの気付きを、一切誰にも口にしなかった。
それでもなんだか、幻太郎さんからいただいたものの最後の一つを消費するときはいつも、私は少しさみしいと思ってしまうのだ。
「お誕生日おめでとうございます」
「ありがとうございます」
座卓を挟んで向かい合った幻太郎さんがかしこまって頭を下げたので、私もそれにならう。二十歳も過ぎれば誕生日なんてそんなに仰々しいものでもないと思うのに、わざわざそんなことをしてみせるのがなんだか幻太郎さんらしくて顔を見合わせて二人で笑った。
いつもの通り幻太郎さんの家で、いつもよりちょっと手間をかけた料理と私の好物を食べて、小さなホールケーキをきゃあきゃあ言いながら二人でやっつけた。なんて素敵な誕生日だろう。おめでとうの言葉ももらって、私はすっかり満たされた気分だ。
「それで……、プレゼントを用意しているのですが、いや、プレゼントなのかな……。とにかく、渡したいものがあるのですが」
さっきまでの穏やかな微笑みを急に引っ込めて、幻太郎さんは困ったように視線を伏せる。今までこんな風に前置きされたことはなかった。どこで覚えてきたの、なんて思うくらいいつもなめらかに渡してくるのに。初めてのかしこまった空気に、なんだか背筋が伸びる。
「その前に少し、小生の恥ずかしい話を聞いてくれますか」
ぴっと背筋を伸ばしたまま頷くと幻太郎さんは微笑んだけれど、それはさっきまでの幸せそうで穏やかなものと少し違う、なんだか無理矢理にがんばって作ってみせたみたいな笑顔だった。
「あなたも気付いているかもしれませんが、俺はこれまで……、あなたになにかをさしあげるときは、いつも、消耗品を選んでいました。ええ、意識して選んでいたのです。なにか思い出と一緒に……形の残るものをと、考えなかったわけではありませんが、どうしても、できませんでした」
でたらめに即興で話をするときはすらすらとよどみなく言葉をつむぐのに、今の幻太郎さんはそれこそ嘘みたいに歯切れが悪い。でもそれは照れているとき、恥ずかしいときの様子だと私はもう知っていたので、じっと大人しく次の言葉を待つ。
「大の大人がとても情けない話ですが、正直に言うと、私は……、怖かったんです。世の恋人がするように服飾品の類をさしあげたとして、あなたは……、もしかしたら、喜んだでしょう。あなたを疑ったわけではありません。ただ、小生は、俺のことは、信じられなかった。俺はあなたに、そんなことをできるに値する人間かと。俺がなにかをあなたに残すことはただ……、あなたに負担を強いるだけではないかと、ずっと思っていました」
そんなことはないです! 思わず叫びそうになって、ぐっとこらえた。ここで一度遮ったら、幻太郎さんはもう二度と、この先のことを話してくれないんじゃないかという気がした。声を上げる代わりにぎゅうっと自分の手を握り締める。
「そんな様ですから、私は自分の出した本でさえ、あなたに渡すことができなかったのです。執筆中にあんなに世話になっているんですから、お礼だと言って渡してしまえばそれだけなのに。まったく情けない話でしょう」
今度の笑みにははっきりと自嘲の色が含まれていた。私の言いたいことは完全に顔に出てしまっていたらしく、「まあそんな顔をせず、もう少し聞いてください」とやんわりなだめられてしまった。そう言われるとやっぱり、私は黙って待つしかない。幻太郎さんの瞳がさっきより少し柔らかくなったから、ひとまずはそれでよしとする。
「それでも……今まで生きてきた中から思うと長くはないですが、そう短くもない時間を共に過ごす中で、俺は少しずつ、うぬぼれていきました。小生は、あなたに許されているのではないか。あなたは、もっと、深くまで、許してくれるのではないか。……うぬぼれだと、そう思っていても、その幸せな想像を止めることはできませんでした」
そこで幻太郎さんは小さく、一つ息をついた。と、目と目が合う。深いのに鮮やかな緑の瞳。不思議なその色合いは、私をいつもドキドキさせる。
「いつの間にか、小生はひどく欲張りになってしまいました。今まで過ごしたくらいじゃ足りません。もっと長い時間、ずっと、俺をうぬぼれさせてください。この何物にも代えがたい幸福な夢を、もっと見させてください」
そう言って懐に手を差し込む。待って。心臓の音がうるさい。幻太郎さんの声を聞き逃したくないのに。
「あなたの誕生日なのに小生がわがままをいうのは少しおかしいかもしれませんが……、まあ、贈り物も用意したということで、聞いてくださると嬉しいです」
今までの台詞。目の前に差し出された箱。期待してしまう。どうしよう。どうしよう。
「どうか、僕と夫婦になってくださいませんか」
そう言って幻太郎さんは深々と頭を下げた。今度はちっとも顔を上げる気配がない。
私の答えなんて決まりきっているのに、まるで刑の宣告を待つ罪人みたいな様子をしていて笑ってしまう。おかしくて、嬉しくて、涙が出てきて、「はい」と言う私はきっと世界で一番間抜けな顔をしていたに違いない。
2018/12ごろ 初公開