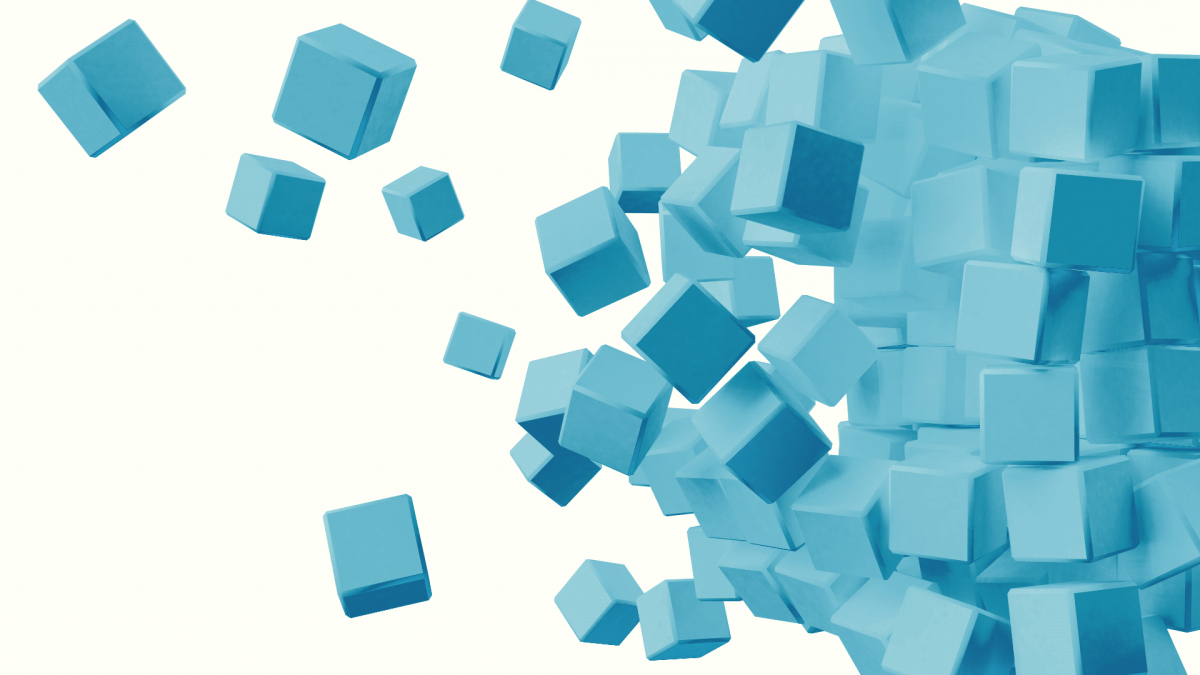銃兎の彼女が媚薬を飲ませられる小話
見も知らぬ男たちに車に押し込まれどことも分からぬ場所に連れてこられたときには、たしかに恐怖しか感じていなかった。それがやわらいだのは、男たちの会話の中に恋人の名前が混じっていたからだ。その名前を聞いた途端、相変わらず敵の多い人だな、なんて急に呑気になってしまう自分が少し笑える。
冷水を浴びせられ、よく分からない薬を飲ませられ、拳を振るわれ、まあ少々ごたごたはしたものの、期待通りに私は今、恋人の腕の中にいる。まるで王子様みたいですね。笑ってやりたかったのに、なんだか少し事情が変わってきた。
体が熱い。
奥底から湧きあがってくる熱さに、身を縮こまらせてじっと耐えることしかできない。じわじわと汗をかいてくる。呼吸もいつもとなんだか違うけど、どう違うのかと言われると早いのだか深いのだか、もう説明できる気がしない。
ここまで抱えてきてくれた銃兎さんが、私をそっとベッドに下ろす。壊れ物に触る手付きのようだ。赤い生地に隔てられた手が頬を撫でようとして、私の異常に気付いたようだった。
「すまない……、怖い思いをさせたな。なにか飲むか? 牛乳でも温めて……」
そこで、はたと目が合った。いつもは自信で満たされているような瞳が、今は不安げに揺れている。その瞳を見て、瞬間、湧きあがる熱がこの人に抱かれたいという欲だと理解した。
「いい、いいです、飲み物は。それより、私、あの、銃兎さん、銃兎さんが……」
そう言う私の目はきっと情欲に染まっているに違いない。銃兎さんも私の奥底の欲望に気付いたのか、手を止めた。
「お前、さっきなにか……」
「おねがいします。さっきから、熱くて仕方なくて、どうしようもないんです。おねがい、銃兎さん、たすけて、銃兎さんの、好きにして……」
言い終わるか終わらないかのうちにぐっと引き寄せられた。よかった。これで楽になれる。そう思って目を閉じたけれど、待てども待てども望んだような展開はやってこない。まるで幼い子どもがするようにぎゅうぎゅうと強く抱きしめられているばかりだ。視界が銃兎さんのスーツで埋まる。あたたかい。ほのかに馴染んだオーデコロンの香りがする。いつもはその香りにすらもとろりとした心地になってしまうけど、それがこんなにつらく感じられる日がくるなんて思わなかった。泣きそうになりながら、そういえばこの人とこんな風にただ抱きしめあうなんて初めてかもしれないな、とぼんやり思った。
いきなりにやってきた体温は、きたときと同じように急に離れていった。私がひいひいと息をついているうちに、銃兎さんはスマートフォンを取り出す。素早く背を向けられたので、表情がわからなかった。さみしい。
「お前は……、おそらく、なんらかの薬物をあのクソどもに投与されている。知り合いの伝手にいい医者がいるんだ。少しいい子にして待ってろ」
大丈夫だ、すぐ戻る。そう告げられて部屋の扉が閉じられる。銃兎さんの声がいつもより硬いことはわかったけれど、それがどういうことなのか考えられるほどの余裕を今の私は持ち合わせておらず、小さなうめき声を上げながら枕に顔を押し付けることしかできなかった。
ツンとした匂いを感じて、意識がふっと浮き上がった。
なんだっけ。どうしてたんだっけ。寝てたみたいだけど、家のベッドより少し硬い気がする、とまで考えて、ここが病院であることを思い出す。
起きましたって言った方がいいのかな、とぼんやり思いながらも、まだこのまどろみに身を預けていたい気持ちが強い。起きる決心がつけられないでいるうちにノックの音がして、誰かが室内に入ってきた。
「神宮寺先生、あいつは……」
「処置は終わったよ。今は少し眠っている。ひとまず大丈夫だろう」
「……ありがとうございます」
銃兎さん。銃兎さんだ。夜中の高速道路をすっ飛ばして、半泣きの私をこの病院まで連れてきた人。心配かけたんだろうな。ごめんなさい。
「血液検査の結果が出ないと断定はできないけれど、たしかに君の推察した通り、強姦事件の際に使われることの多い違法薬物の可能性が高いように思ったよ。くわしい結果が出たら署の方に送ろう」
「感謝します。……後遺症の方は? 依存性のある薬でしょう」
「体質にもよるから、今のところはなんとも言えないね……。点滴を今打ってはいるから、今日は帰宅後も水分をよく摂るように。数日経っても様子がおかしいようなら、また連絡をしてくれるかい」
「……わかりました」
まだ半分寝ている頭には難しい話はうまく入ってこなかったけど、私の話をしているんだということはわかった。こういうことを当事者よりもしっかり覚えて気にするタイプの世話焼きな銃兎さんだから、申し訳ないけれど今回もお願いしよう。きっと銃兎さんの好物を作るから許してください。
「それから、腕にも打ち身があったよ。カウンセリングで聞いたところによると、殴られそうになったときにとっさに頭をかばったそうだ」
「殴られ……っ」
「静かに。彼女が起きてしまうよ。こちらは全治二週間というところかな。のちのちまで残るようなあざではないはずだ。湿布を出すから、少なくとも一週間はきちんと取り換えてあげるようにしてね」
そうだった。殴られそうになったということを、銃兎さんには言ってなかったんだっけ。特別隠そうとしたんじゃなくて、言い出すような余裕も暇もなかったからなんだけど、怒るかなあ。心配性だからなあ。
「医師として言わせてもらうなら……、こういった事件に巻き込まれたあとは、まず真っ先に病院を頼ってほしいな」
「返す言葉も……」
「珍しく詰めが甘ェじゃねえかよ。オンナのことになるとウサポリ公も形無しかァ?」
「うるせぇぞ左馬刻」
「おお、こえーこえー」
ああ、違うんだよ。きっと普段の銃兎さんなら病院で検査を受けることを忘れたりしなかったはず。私があのとき情けなく縋り付いたりなんかしたから、銃兎さんは早く安心させてやらなくちゃって思ってすぐさま家に連れ帰ってくれたんだよ。
そりゃあ、お母さんにだってこんなに言われたことないってくらいに小言をもらうこともあるけど、全部全部、私を心配してくれてるからなんだよ。信じられないくらいに情が深い人なんだよ。
早く銃兎さんを安心させたい。心配かけてごめんなさい。助けてくれて、病院まで連れてきてくれてありがとう。もう大丈夫です。
「じゅうとさん……」
大丈夫だって言いたかったのに、口から出てきた声は自分でも驚くくらいへにょへにょしていた。すぐそばに誰かの気配がやってくる。馴染んだオーデコロンの香り。
「起きたか?……まだ眠そうじゃねえか。もう少ししたら点滴が終わるから、そしたら二人で家に帰ろうな。それまで寝てていいぞ」
「だいじょーぶ、です……」
「ほとんど目ェつむってるくせになに言ってんだ。ほら、ゆっくり休んでろ」
違うんです。私はもう大丈夫です。だから安心してくださいね。また明日からは、いつも通り楽しくすごしましょうね。
言いたい言葉はうまく音にならずに口の中でもごもごと消えていく。いつもみたいに「お前はどうしてそう能天気なんだ」って笑う銃兎さんが見たかったなあ、と思ったのが最後で、私はそのまま夢の中に落ちていった。
2018/12ごろ 初公開
銃兎がただただかわいそうな話。