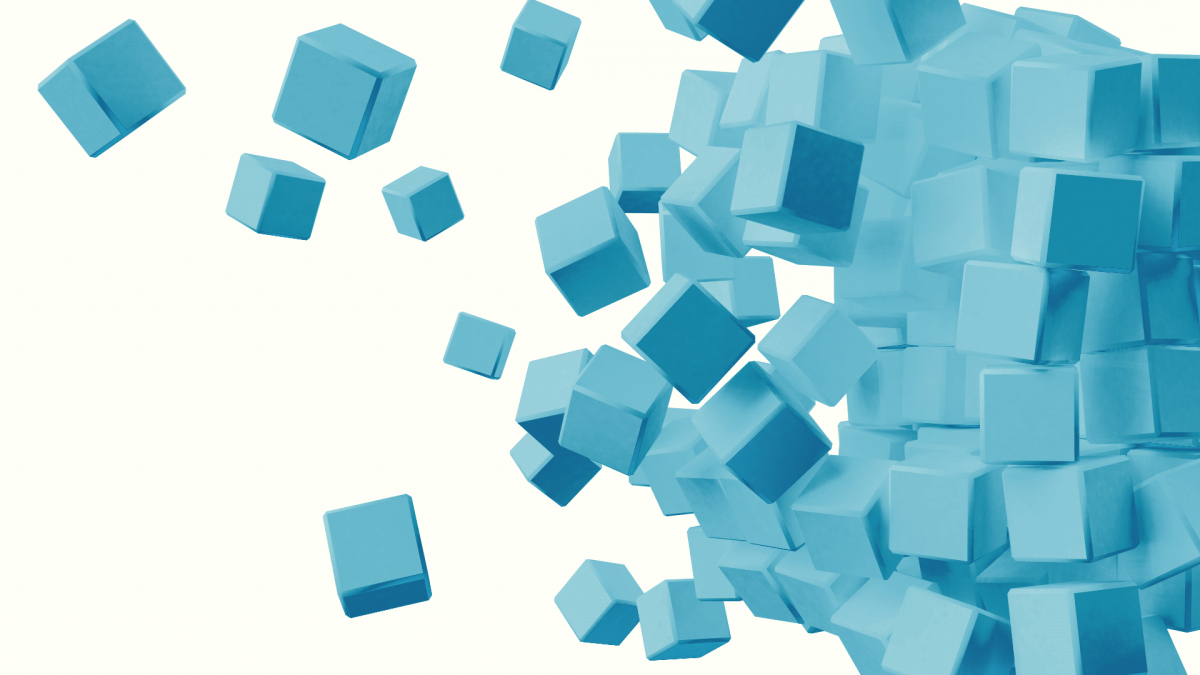好奇心で私は死ぬ 02
焼きが回ったもんだぜ。茶化したように内心吐き出してみても状況は変わらなかった。
「大丈夫っすか? ときどきああいう強引な手合いがいるんで、気ィ付けてくださいね」
「いえどうも……、アリガトウゴザイマス」
どうして、繁華街の片隅で、山田一郎と向かい合って話なんてしてるんだろう。
いつものように休日にこそこそ山田一郎をつけ回し、彼が仕事をしていると思しき間にウロウロとウインドウショッピングをたしなんでいたところ、タチの悪そうなナンパに捕まったのが運の尽きだった。普段チンピラと接している油断から、まだこれは本当に危ないタイミングじゃないな、と適当にあしらっていたのが悪かったのか、そのうち焦れてきたらしいナンパ男が私の手を強引に掴もうとしたところで、いつの間にやら外に出てきていた山田一郎が間に入ってくれたのである。
なんの後ろ暗さもないのなら、エエッ元TDDの山田一郎に助けてもらえるなんて最高じゃんロマンス始まっちゃうかも! などと思う場面だが、あいにく私は山田一郎という男に対して後ろ暗いところしかないのだ。何事も始まらないうちに、ここからとっとと立ち去ってしまいたい。
「あの、どうもありがとうございました。気を付けます。それじゃ」
「お姉さん一人なんすか? そこまで送りますよ」
「エッ」
めっちゃ嫌そうな声で「エッ」て言ってしまった。山田一郎もちょっと面食らっている。いや、でも、これは、さっきタチの悪いナンパに遭遇したからで、そう不自然ではない反応だったと思いたい。
「や、ほらもう暗い時間だし、ああいうの増えてくるかなって。モロにその現場見たあとだとやっぱちょっと心配で」
「いえ、もう駅行って帰るんで大丈夫です。知らない人によくしてもらっても申し訳ないですし、お礼とかもできないんで」
「お礼なんて気にしなくても……、あ、じゃあそこでジュース奢ってください。それがお礼ってことで。……まあ一番は俺が安心したいだけなんすけど」
どっすか? と人の好さそうな笑顔を向けられて、私は負けた。これ以上問答してたらなんだか私の方がイケメンに無茶を言っている構図になってしまう気がする。ここで強く断ることのできない小心な自分を恨めしく思いながら、「じゃあ、駅まで」ともごもご答えた。ああ。
手近な自動販売機に硬貨を入れると、山田一郎は迷いなくコーラのボタンを押した。続いて私も適当なコーヒー飲料のボタンを押して、二人で並んで歩く。喋る気なんてなかったのに、山田一郎がフラッと世間話なんて振ってくるものだからつい答えてしまって困った。
最近の缶コーヒーのバリエーションについて、なんていう心底どうでもいい話題について適当に話しているうちにイケブクロ駅が見えてきて、心の中でめちゃくちゃ安堵の息を出した。早いところこんな拷問からは解放されたい。改札目指して走り出してしまいそうになる足をなんとか押しとどめて、駅へと入るところで横の男に声をかけた。
「ありがとうございます。ここからはもう平気なんで。お手数おかけしました」
あーよかったよかったこんなのは二度とごめんだね、と内心思っているのを見透かしているように、山田一郎はふっと笑った。
「いえ、帰り道気を付けて。また変なのに引っかからないでくださいね」
なにもおかしくはないはずのそのセリフが、まるでなんだか変なおまじないでもかけられたみたいで、背中がぞわっと粟立ったような気がした。その感覚を振り払うように足早に改札へと向かう。あんなに熱心につけ回していたくせに、まだ山田一郎がそこにいたらと思うとなんだか怖くて、後ろを振り向くことはできなかった。
その一件で、どうやら私は山田一郎に顔を覚えられてしまったらしい。駅や道で偶然出会ったときに、あの人の好さそうな笑顔で「どもっす」と挨拶されるようになったのだ。そんな路上でちょっと助けて駅まで送っただけで友達みたいになることある? と思ったけれど、そういえば尾行しているときもちょこちょこ道で会う人と挨拶したり話したり、はたまた困っていそうな人に声をかけたりと、思い返してみれば山田一郎とはそういうタイプの人間であった。さすが友達の多い人種、根本的に私とは作りが違うんだろう。
山田一郎と面識を持ってしまったせいで、尾行の方は完全に滞ってしまった。うっかり見つかってしまった日には「どうしたんすか?」とニコニコ話しかけられるのが容易に想像できてしまう。山田一郎は口が上手いし、大きくてなんか圧があるので、話しているうちにあなたをつけていましたと白状してしまいそうな気さえして、恐ろしかった。
それでも、碧棺左馬刻の事務所にファイルを送ることは止めたくなかった。完全に自己満足だが、そういうものこそ、人間、意地になってしまうものである。せめてなんらかの有意義な情報を引き出せないかと立ち話に付き合ってみたりもしたが、あまり成果はよくなかった。逆に名前や連絡先などをいつの間にか交換してしまったりして、山田一郎のコミュニケーション能力にただただビビっていた。詐欺師始めたらあっという間に億万長者になれるよ、とうっかり言いそうになったけど、それをやらないから山田一郎なんだろうなというのが同時に頭に浮かんできて、一人で打ちのめされたりもしていた。陽の若者、まぶしい。
さして使われることもないだろうと思っていた連絡先だが、意外なことに山田一郎からはときどきメッセージがやってきた。それは大抵、近所の犬とか会心の出来だったらしい自作のから揚げとかの写真が添付されている日記みたいな内容で、碧棺左馬刻に送る情報の足しになることはほとんどなかった。それなのに私は、馬鹿みたいに律義にいつも返信を返していた。碧棺左馬刻に送れるような情報を得るためなのか、山田一郎の日常生活を探っている後ろめたさなのか、それともこの関係を少し楽しんでいるのか、もう自分でもよく分からなかったけれど、とにかく二言三言のラリーが続いて終了する、というのがお決まりの流れになっていた。
どういう話の流れだったかはもう曖昧だが、私は再び「どうしてこんなことに」と内心吐き出していた。なんか今、山田一郎と普通にお茶しているのである。
そのシリーズ好き、だったか、それ見に行くつもりなんですよね、だったか、どこかで私が口を滑らしてしまったのは確かで、ついさっきまで山田一郎と映画館に行っていた。ちょっとマイナー目ではあるものの、娯楽系痛快アクション映画だったのは不幸中の幸いと言える。これがまさか恋愛映画だったりしたら、私は今ごろ、謎の気まずさに襲われていたに違いない。
「あそこよかったっすよね。あの中盤の、でかいトラックでカーチェイスするシーン。すげー迫力あって。あれもうちょっと見てたかったっすね」
「あー、分かるかも。でも今回、ストーリー的にはヒロインあんまり必要ない感じでしたね。その尺で相棒の方もうちょっと掘り下げてほしかった」
「あ、たしかに。相棒の方ちょっと投げっぱだったすね。スピンオフやってくれねえかな」
山田一郎の情報を引き出すためにはもう少し親しくなるべきか? いやあまり親しくなりすぎるとまずいのか? 迷ったものの、考えたところで私が最適解を見出だせるとも思えなかったので、早々に諦めて流れに身を任せることにした。下手の考え休むに似たり。それに、映画の話に罪はない。
しかし、解放していた脳細胞を一気に集めなければいけない事態が起きた。
「スンマセン、俺ちょっとトイレ」
トイレに行くのはいい。全然いい。生理現象だもの、どんどん行きな。
問題は、山田一郎がテーブル上にスマホを置いていったことである。
あのとき職場で、よく分からない『今のところ合法らしい飴』は断ったものの、実を言うと別のものは受け取っていた。それは、端的に言えばストーカーがよく使うという、スマホに仕込む盗聴・監視アプリだった。
どうする。スマホにすぐ差せる端子付きのメモリに入っているから、今なら、このアプリを山田一郎のスマホに仕込むことができる。すぐダウンロードは終わると聞いたけれど、どれくらいで山田一郎が戻ってくるか分からない以上、やるのならば早く決断しなくては。
さすがにちょっとやりすぎなんじゃないの。犯罪スレスレなんじゃ。というか犯罪かも。でも、ここのところ、ろくに送れるような情報を集められていない。碧棺左馬刻に送るファイルも滞っている。
別に誰かに頼まれたわけじゃないんだから、そんなに躍起になって山田一郎の情報なんて集めなくてもいいんじゃないの。
いやだ。私は送りたいんだ。誰に頼まれたわけでもないけど、私がそうしたい。私があの人に、ただ、送りたいんだ。
自分でも驚くくらい脳みそが早く動いて、手も同じくだった。過去数年なかったし、今後数年もきっと無理だろうというくらいのスペックを記録した。そうして私は、無事に山田一郎のスマホに、監視アプリを仕込んだのである。
「いやスンマセン、結構トイレ混んでて。お待たせしました」
「大丈夫。気にしないで、全然」
正直、家に帰って若干後悔というか、罪悪感に襲われたのは事実である。犯罪かもじゃないよ普通に犯罪だよこんなの。いや法律とかよく知らないから本当にそうかは分からないけど、万一犯罪じゃなかったとしても、家族でも親戚でもない未成年のスマホに勝手に監視アプリ仕込みましたとか社会的にアウトすぎるでしょ。
やってしまった感満載でパソコンの前でうだうだとクッションをつつく。このまま寝てしまえばいいのだ。そうしたら、これはここで終わる。山田一郎のスマホに仕込んだアプリと、私の手元にあるアプリを正式に連携させなければ、山田一郎の情報は私に流れてくることもなく、ただ変なアプリが山田一郎のスマホの奥底に眠るだけになる。
そうするのが一番平和な方法だと私の理性は叫んでいたが、結局数分ののち、私はエイヤッという気合とともに連携ボタンを押していた。「通信中」のゲージがしばらく現れて、パッと画面が変わる。マップ上に浮かび上がる「現在位置」を指し示す点。
うわあ。これ、うわあ~、すごくない?
テンションが上がって盗聴もしてみたら、『二郎、もう風呂入っちまえよ』『うん、わかったよ兄ちゃん』という声といくらかの生活音が聞こえて、すぐ切った。なんというか、そういうプライバシーを知りたいわけじゃないと思ったし、盗聴はあんまりやっていると電池を食うのでバレやすいと聞いていたのもある。でも仕事の電話は聞いておきたいと思ったので、通話が開始されたら録音してこっちに送信するように設定はしておいた。ああ、理性って儚い。
山田一郎の一日の足取りをマップ上で追ったり、録音された電話の内容を聞いたり。言葉にするとそれだけだが、今まで滞っていたのはなんだったのかというくらいにみるみる情報が集まった。電話口で時折いかにも怖そうな声の主が依頼をしてきたりもしたけれど、そういうときはどちらも絶対に依頼内容については口にしなかったので、なんだか山田一郎の新しい一面を見てしまったなあと思ったりしていた。
ものの数日で碧棺左馬刻に送るファイルはいっぱいになり、私はご機嫌で内容をまとめなおしていた。私と接触したときのことも書いた方がいいかと迷いもしたが、なんだか気恥ずかしかったし大した内容でもないので端折っておいた。
私は浮かれていた。イベントごとの度に街に繰り出してはウェイウェイと騒ぎニュースになる若者を笑えないくらい、完全に浮かれていた。
そんな有様だったものだから、「あのシリーズのDVD発掘したんでうちに上映会しにきません?」という山田一郎からのメッセージにも、「やったー楽しみ!」と勇んで返事してしまったのである。もう越えるべき一線は越えてしまったんだ、こうなりゃとことん山田一郎の情報を搾り取ってやるぜ。
やってやるぞと意気込んでいたのはせいぜい前日までで、山田家の玄関に来たころにはもうだいぶ後悔していた。だってここに来て分かるようなことって、大体盗聴すれば分かったんじゃない? 変に約束取り付けてここまで来ることなかったのでは。
しかし山田一郎の部屋に通されて、例の映画のタイトルコールが流れるころには、わーこれずいぶん前に見たから内容忘れちゃってたんだよななどと、もうそんなことは頭からすっ飛んでいた。考えても仕方のないことを深く考えないのは私のいいところなのである。
そうしていくらか雑談を挟みつつの映画鑑賞が終わり、勇壮なエンドロールが流れ出した。無意識のうちに張り詰めていた息を吐きだして、持参していたペットボトルのドリンクに手を伸ばす。いやーよかった。やっぱり初代って思い入れが違う。いい。
「やっぱ初代いいっすねー……」
「ね……、これがあるからこその今ですよ……」
ゆったりと映画の余韻に浸っていた。山田一郎がいきなり「ところで、お姉さんに話があるんすけど」などと言い出すまでは。
えっ待って待って、待ってほしい。私は山田一郎に対して後ろ暗いことしかないのだ。話ってなんだ。以前から山田一郎の情報を探っていたこと? 今まさに山田一郎のスマホに監視アプリを仕込んでいること? それともそれらで得たものすべてを碧棺左馬刻に送っていること? どれがバレているんだ。まさか全部なのか。もしかして映画鑑賞会なんてのは口実でこれが本題だったのでは。リビングの大きなテレビで見るのではなく、山田一郎の部屋に通された時点であやしいと思うべきだったのでは。深く考えずに適当にハイハイと流れに身を任せてしまうのは私の悪いところなのだ。
私の内心の焦りを理解しているのかしていないのか、山田一郎は穏やかな顔のまま、表情を変えない。
「お姉さん、俺のこと、ストーキングしてますよね」
断定系だった。ということは、やっぱり私のしていることのいくらかは山田一郎に知られているんだろう。肯定すべきとも否定すべきとも思えなくて、ただ喉の奥から「ひぃ」とどっちともとれないか細い声が出た。さっき飲み物を飲んだばかりなのに、喉の奥がからからに乾いていた。
「俺のこと、結構前から見てますよね。最初はへったくそな尾行してて、なんもしねえなら放っとくかって思って放っといたらマジでなんもしねえし。俺が適当な口実作って近付いてみたら、逆にそっちは全然近付いてこなくなるし。連絡先交換しても俺から送るばっかだし。そのくせスマホ置いといたらここぞとばかりに監視アプリ仕込むし」
悲しい事実。私のやってること、ほとんど山田一郎にバレていた。ここは文字通り山田一郎のホームである。よくも今まで好き勝手してくれたなと制裁を与えられるんだろうか。でもここに至るまでずっと放置してくれたんだからどうにか見逃してくれたり、しないか? しないか。だってめちゃくちゃ二人っきりで呼び出されているもの、今。
「お姉さん、マジであんな俺をめちゃくちゃ好きですみたいな目で見てるくせに、肝心なとこで変にシャイっすよね」
「ヘァ」
は? って言いたかったのに、からからの喉と緊張のせいで変な声しか出なかった。
「俺のファンってだけの女の子ならいっぱいいるのに、なんだろ、お姉さんは距離の取り方よく分かんねえし、完全にストーカーだし、それなのに会うと素っ気なかったり普通だったりして、あーも、なんすかね、俺、もう……」
好きです。呟きとともにぎゅうと抱きしめられる。
いや待って。違うんですよ。私、特別あなたのファンというわけではなくて、むしろ碧棺左馬刻のファンなんですよ。あなたにストーカーみたいな真似していたのも、碧棺左馬刻にその情報を送っていたからなんですよ。
うっかり本当のことを全部話しそうになって、恐怖心がブレーキをかけた。待って。山田一郎は多分、私のやっていることをほとんど知っているだろうけど、その動機だけは間違って認識しているのでは? だってあんなに盛大に仲違いしたらしい碧棺左馬刻のためだということを知っていたらきっと、「アイツに頼まれたのか」とか言われているはずで、こんな、抱きしめられたりしているはずは、ない。
もし本当のことを知られたらどうなるだろう? 私が勝手にやっているとはいえ、これはスパイと言われてもなにもおかしくないような行動だ。山田一郎。この数か月見ていて、優しいだけの男じゃないのだということを私はどこかで感じていたはずだ。私に回された腕を見てください。これ、ちょっとその気になれば私の首とかコキャッといけるのじゃないか。
私は観念して、震えそうになる両手をなんとかがんばって山田一郎の両腕に添えた。抱きしめる腕に嬉しそうな力がこもって、すり、と首元に鼻を寄せられる。
大丈夫。私はもう馬鹿なことをしたりしない。自分に言い聞かせるように心の内で呟く。きっと私は山田一郎を好きになる。だって世の中、イケメンに敵うものなんてないのだから。
2018/12/15 初公開
山田一郎だって10代の若者なので、自分のことを好きだという女(と山田一郎は思っている)と身近に接して色々感情振り回されたら好きになっちゃうのではという話。