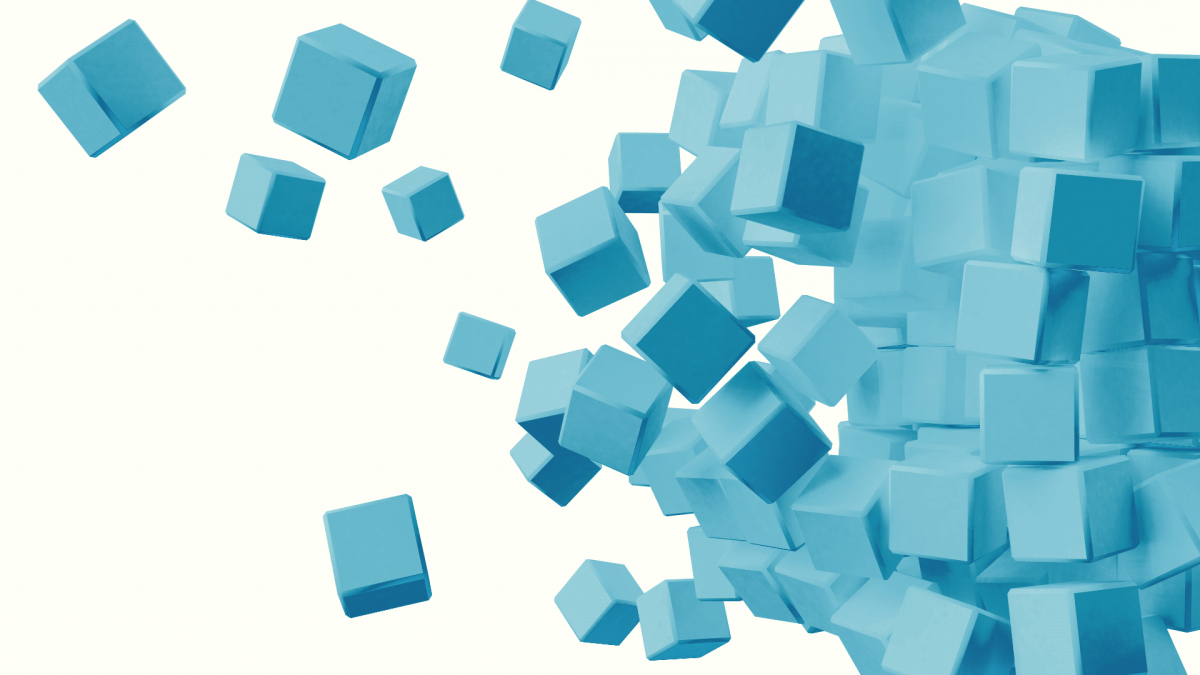好奇心で私は死ぬ 01
ラップなんて早口でなに言ってるかよく分かんないし、なんか男ばっかりがやってるやつでしょ、興味なし、パス、と以前の私ならば間違いなく言っていただろうが、そのようなことを言う私は綺麗に折りたたんで捨てた。なんでかと言うと理由はとても簡単で、一世を風靡したラップチーム、The Dirty Dawgのメンバーである碧棺左馬刻の顔を、私はようやくそのとき知ったのである。
そりゃーもうどえらいかっこよかった。たまたま立ち読みした雑誌に載っている彼の顔を見た瞬間の感想は「えっ好き……」だったし、記事の説明で彼がラップをしているということを知った瞬間の感想は「いやあイイですよね、ラップ。男らしいし、カッコイイ」だった。
ついでに言うとそれまでの私はとあるバンドのそこそこな古参ファンで、それなりに整った顔をしているギタリスト目当てだという新規ファンが現れるたびに内心「は? 顔ファンかよ……、ちゃんと音楽聞いてくれないとさ~」などと思っていたのだが、そのようなことを言う私も丁寧に切り刻んでゴミの日に出した。いやー、世の中、イケメンに敵うものはないよね。
それからの私は音源を集め、行けそうな場所でバトルやサイファーをしていると聞けば即駆けつけ、メディアに露出するとなると欠かさずチェックしと、なかなか熱量のあるThe Dirty Dawgのファンになった。そのころは大抵四人揃って活動していたので、The Dirty Dawgのファンだったと言ってもまあ間違いではなかっただろうが、正確に言うと、やっぱり碧棺左馬刻のファンだった。きっかけは顔であっても追っかけているうちにどんどん活動内容も好きになっていくもので、毎晩寝る前には彼のラップを聞いていたし、朝起きては彼のラップを聞いていた。雑誌の短い一言二言のインタビューを何度も何度も繰り返し読み返した。記事の写真を引き延ばしてポスターにしてベタベタと部屋中に貼っていたのは、今思うと流石にちょっとキモいかと思うけれども。
そんな生活をしばらく続けていたものだから、The Dirty Dawgが解散するとなったときの私は大変ひどい有様だった。時を同じくしてなんやかやと国に変動が起きていたようだけれど、毎日のニュースをぼんやりと聞き流し、選挙のハガキがきてようやく参政権を思い出すような私には、そんなことよりも碧棺左馬刻の情報がこの先これ以上出てくることはないだろうということの方が重大であった。家にいる間はビャービャーと泣き通す生活を一週間ほど続けて、姉にひどくウザがられた。
傷心していても時間は流れていくもので、もうこの悲しみが晴れることなんてない、と最初は思っていた私も、少しずつ日常に戻り始めた。というより、少し前に就職した企業がにわかに忙しくなり、それどころではなくなってきたというのが大きかった。
大学に行くほど賢くないけど卒業してすぐ就職というのも遊べなくて嫌だなあ、と完全にバカの感覚で入った専門学校を順調にドロップアウトしていた私は、タダ飯食らいを置いておく余裕はないと家族にせっつかれて、結局仕事口を探していた。『未経験者歓迎、アットホームな職場です』の定型句はともかく、ペラペラの無料タウン誌に載っていた相場よりお高めの給金を提示している事務職に惹かれてホイホイと面接した結果、あれよという間に採用されて契約社員に収まったときは、私ってば本気になればわりとやるじゃん、と思ったものだ。
だがやはり美味しい話には裏があるもので、なかなかお堅そうでカッコイイじゃんと思っていた『金融業』というのは、ほんの少し、若干、わりと、半分くらいはヤバめの方々と繋がっている高利貸しをやんわりと言い表した文句であることを、私は入社の書類にハンコを押してから知ったのだった。
明らかにタチの悪いチンピラ、道を歩くときにすれ違うのなら目を逸らすべきタイプですと全身で表している人間が出入りする事務所に最初は慄いたものの、与えられた仕事をほどほどにこなし「ええ~、そうなんですか」「ありがとうございます」と無難な言葉をニコニコと吐き出していれば、あちらもニコニコと飴なんかくれたりしたので助かった。人間、愛想って大事である。
お給料はなかなかいいとは言っても、やっぱりヤバめの人たちと関わるような仕事ってよくないんじゃないか。でも入ってすぐ辞めるっていうのもな。お局様みたいな人もいなくて事務員は少人数だから働きやすくはあるし。でもこの先ずっとここにいるわけにもいかないでしょ。今のところ予定はないけど結婚とかするとき面倒そう。いやでも正直なところ私って将来のこととか真面目に考えるタイプじゃないんだよな。今日フツーにご飯と寝るとこがあって楽しく生きられればそれでイイって感じ。うーん、とりあえず半年くらい働いてから考えよ。
そんな風にぼんやりと自分の進退について考えていた私だったが、事務所でも一番下っ端のくせにやたら格好だけはイキがっている空気の読めないチンピラが、よりにもよって高校時代の友人と遊んでいるときに声などかけてきて友人からとんでもない目で見られるという事件が発生したため、私はあっさりこの仕事を退職する決意を固めたのであった。
そうは言ってもやはり相手が相手なので、入って数ヵ月も経たない間にいきなり辞めますと言うのはなんとなく恐ろしい。普段の仕事で彼らの報復の一端を知っているため、なおさらである。まずはいつも事務仕事を振ってくれる立場の比較的穏やかそうなおじさんに相談することにした。
「あの~、スミマセン。ちょっとご相談したいことがあるんですが……」
「いいよ、ちょうどコーヒー湧いたとこだったから」
おじさんがにこやかに答えてくれたところで、スマホが鳴った。片手で謝るおじさんに業務上の笑顔を返してコーヒーサーバーに向かう。ホルダーに入れればオッケーの使い捨てカップはエコに真っ向から対抗しているが、事務員を洗い物のストレスから解放する素晴らしい存在である。
「もしもし。……はい。……ええ、はい。……え、ハマの碧棺ですか」
「え」
「うーん、じゃあ上に、ええ、そうです。……はい、はい。……はい、分かりました、こっちもこっちでなんとかしますんで。はい。はい、よろしくお願いします。……はい、失礼します。……ごめんね、お待たせ」
「いえいえ。大丈夫ですか? お仕事入ったんじゃ」
「いや大丈夫、こっちの方はそう急いでできることもないから」
相変わらずおじさんは穏やかそうだ。いけるんじゃないか? というつもりがしてきて、気になったことをズバッと聞いてみることにした。
「あの、ハマの碧棺ってThe Dirty Dawgの碧棺左馬刻ですか?」
「あ、そうそう。アイツって一般人にも有名なんだっけ」
「ってことは、こっちでも有名なんですか」
「うーん、まあそれなりにねえ。ウチと危ないことになることはそうそうないから助かるけど、ほかでは結構やってるらしいよ」
「そうなんですね」
そこでおじさんはコーヒーを啜ってニヤッと笑った。
「なに? ミーハー?」
「へへへ」
「若いね~。俺も若いころは地方営業ばっかの売れないアイドルにハマったりしてさあ」
そう言うおじさんと目が合って、通じあったことが分かった。私はこの日のためにここで愛想をよくしていたんだよ!
「ところで相談したいことって?」
「あ、今度の連休に姉とちょっと旅行に行くんですよ。おみやげってどんなのがよさそうですかね」
「あ~、俺あれ、あのおみやげコーナーによくあるご当地クッキー好き」
期待したとおり、おじさんはときどき碧棺左馬刻の情報をちらほらと教えてくれるようになった。その内容はどこそこの組の誰それを病院送りにしたらしいとか、なんとかって組の息のかかった事務所を潰したらしいとか大抵はろくでもないものだったが、それでも碧棺左馬刻が少なくとも今そういうことをできるくらい元気であるということを知れるのは嬉しかった。
推し、活動していなくても、元気に生きていてくれればそれでいい。
いつかは辞めようと思っていたはずなのに、目先の喜びに釣られてずるずると勤め続けた結果、いつの間にやら数年が経っていた。
ところで、私がよく行く場所の一つにイケブクロがある。電車で一本の場所に昔から住んでいるので、行動範囲を特に変えないままこの歳になったのだ。
The Dirty Dawgのファンだったころに知り合った同担の何人かは、実際にヨコハマに移り住んだらしい。私はそういう、あわよくば会えないかというか、ガチ恋というか、そういった風に碧棺左馬刻を好きだったわけではないので、そこまではしなかった。
碧棺左馬刻と世にも盛大な仲違いをしたという山田一郎のナワバリがイケブクロだということはよくよく知っていたが、イケブクロという街をそれなりに気に入っていたし、そういうので行く街を変えるってのもなんか違うなと思ったので、私の行動範囲はそのままだった。あと単純に実家を出たくなかった。
駅からすぐの公園でよくサイファーをしているという話は知っていたけれど、The Dirty Dawgが解散して以来、山田一郎を見ることもなくなった。私の意識のピントがもうズレてしまったというのもあるかもしれない。
だからそれは、本当に偶然だった。
ぶらぶらと特に目的もなく冷やかした店の自動ドアをくぐったとき、目の前を横切った男が山田一郎であることにふと気づいた。The Dirty Dawgにいたころより少し大人びているようだったが、それでも毎日のように追いかけていたチームのメンバーを見間違えるはずがない。その後を追いかけるように足を向けたのは、久しぶりにメンバーをこの目で見た懐かしさもあったけれど、結局、単に好奇心だった。
山田一郎はそう歩くことなくチェーンのカフェに入って、なにやら店内で飲むことにしたようだった。私も季節限定のラテを頼んで、彼からそう遠くもなく近くもない席に座る。ちらりと盗み見ると、慣れた手つきでスマホをいじっていた。
ぼんやりとラテを飲んでいると、The Dirty Dawgを追いかけていたころの懐かしい記憶がなんだか思い起こされる。それだけならよかったのに、同時によろしくない考えも私の脳裏にじわじわと押し寄せてきていた。
あわよくば会えないかというか、ガチ恋というか、そういった風に碧棺左馬刻を好きだったわけではないけれど、ただ好きでいられればそれで幸せなんていう大人しいファンだったわけでもない。できることなら、碧棺左馬刻を応援している人間がここにいるということを、彼に知ってほしかった。
まだThe Dirty Dawgが活動していたころにこれでもかというくらい調べたが、碧棺左馬刻に差し入れや手紙、プレゼントの類を送ることのできる窓口はどうも存在しなかった。彼の職業のことを考えれば、まあ当然かもしれない。それじゃあとバトルのときには必死になって声援を送っていたけれど、それすらも彼には必要なかったんじゃないかと思う。その場にいる誰もが彼に一つの声もかけなくったって、碧棺左馬刻という男は毛の先ほども気にせずにいつも通りにカッコよくって素晴らしいラップを披露できただろう。多分、これから先もずっと。
そういう碧棺左馬刻が好きか嫌いかと問われると、そりゃまあカッコよすぎてしびれるにも程があるし大好きですと答えるが、そうじゃなくて、彼にちゃんと返したかったのだ。
碧棺左馬刻がThe Dirty Dawgで活動して、ラップをして、ただそこにいるそれだけで、心が癒されて明日もがんばろうと生きる気力が湧いてきた。あなたにそれだけエネルギーを貰っている人間がいるということを知ってほしかった。そういうエネルギーをくれてありがとうという感謝を、なにかちゃんと彼が必要としている形にして渡したいという気持ちを、私はずっと抱えていた。
もう一度こっそりと山田一郎に目を向ける。まだカップの中身はなくならないようで、スマホをいじったりときどき窓の外に目を向けたりと、周りの客とそう変わらない様子で過ごしている。
今なら、やれるんじゃないか。心の中で馬鹿な自分が囁く。
犬猿の仲の相手の情報って、そりゃ喉から手が出るようにほしいものじゃないけど、あって困るものじゃないんじゃないか。今なら碧棺左馬刻の事務所の住所くらいであればわかる。私だってイケブクロの街のことならそれなりに知っている。山田一郎のことも、まったく知らないわけじゃない。
よし、やろう。さすがにこのあとすぐに行動に移すと感づかれるだろうから今日はなにもしないけど、きっときっとお前の動向と情報をきっちり掴んでやるぞ。
もしも少し未来の自分がこのときに戻れるのならば、たとえ病院送りになろうとも己をボコボコにして絶対にやめろと言い聞かすのだけれど、このときの私はそんなことも知らずに、ただ馬鹿な考えに酔っていたのだった。
実際に何度かやってみて、尾行ってめちゃくちゃ難しいんだと私はよくよく身に染みて理解した。推理ドラマみたいに満足のいく尾行ができたことなんて一回もない。
本で読んだりして知ったことだけど、尾行というのはそもそも何人かでチームを組んでやるものなんだそうだ。かと言って、こんな馬鹿の自己満足に付き合ってくれる人間に心当たりなんてあるはずもなく、結局一人でコソコソと真似事の尾行を繰り返すしかなかった。
しかし、まったく収穫がないというわけでもなかった。いつの間にやら営み始めたという萬屋稼業は思ったよりも繁盛しているらしく、山田一郎は毎日イケブクロ近辺を飛び回っていた。掃除全般、子どもやペットの世話、家具組み立て、引っ越しの手伝いなどなど、その業務は多岐に渡り、常連と言っていいくらいに頼んでいる人もちらほらいる。実際に萬屋ヤマダを利用したという私の知り合いも発見したので話を聞いてみたが、顧客からの評判は上々のようだ。そうそう外からのぞけないような場所に赴くこともあったので、そのときは大人しく諦めるほかなく、多分似たようなことやってるんだろう、とぼんやり想像したりしていた。
仕事の合間やプライベートで行く、気に入りの店の把握は思ったよりも楽だった。The Dirty Dawgで活動していたころの山田一郎の好みを思い返して、その手のタイプが好きそうな店をいくらかチェックしていればよかったからだ。この辺の店好きそうだなと思いながら仕事帰りに歩いていたときに実際に山田一郎が現れたときは飛び上がって喜びたくなった。
仕事以外のほとんどの時間を山田一郎の情報を探ることに費やしていたと思う。それまでほとんど断ったことのなかった残業をちらちら拒否するようになったので、仕事の時間も削っていたと言っていいかもしれない。急にそんな風になったものだから、職場の人にもどうしたのと驚かれ、「いやあ最近気になる人ができて」と本当じゃないけれどギリギリ嘘でもない感じのことを話したところ、入社以来浮いた話がなかったアイツにもついに、などとちょっと盛り上がったりしてしまって若干後悔した。それでも盛り上がったついでに最近はこういうお店なんかが若い子にも人気で、なんていう情報を教えてもらったのは割と助かった。押しが大事だよと差し出された『今のところは法規制されてないまだ合法な飴みたいなもの』は丁重にお断りした。
そうやって少しずつ集めた山田一郎の情報を夜中にぽちぽちと整理するのが私の、私だけの素晴らしい時間だった。一つ一つは小さな情報でもまとめてみるとそれなりの量になるもので、だいたい一か月から三か月に一回くらいのペースで、できるだけ見やすいようにとまとめたファイルを碧棺左馬刻の事務所宛に送った。住所はやっぱり職場のデータベースを漁ると出てきたので助かった。
碧棺左馬刻はこのときどき送られてくるファイルをどう思ってるだろう。もちろん無記名で送っているけど、不審な郵便だと思われて処分されているのだけは嫌だ。最悪、変な奴とか気持ち悪いとか思われててもいいから、せめて一度だけでも碧棺左馬刻本人に目を通していてほしい。これは私がようやく送ることができる、彼へのファンレターだから。
2018/12/15 初公開
コミカライズが始まる前に全部捏造で書けるうちにと書いたやつ。