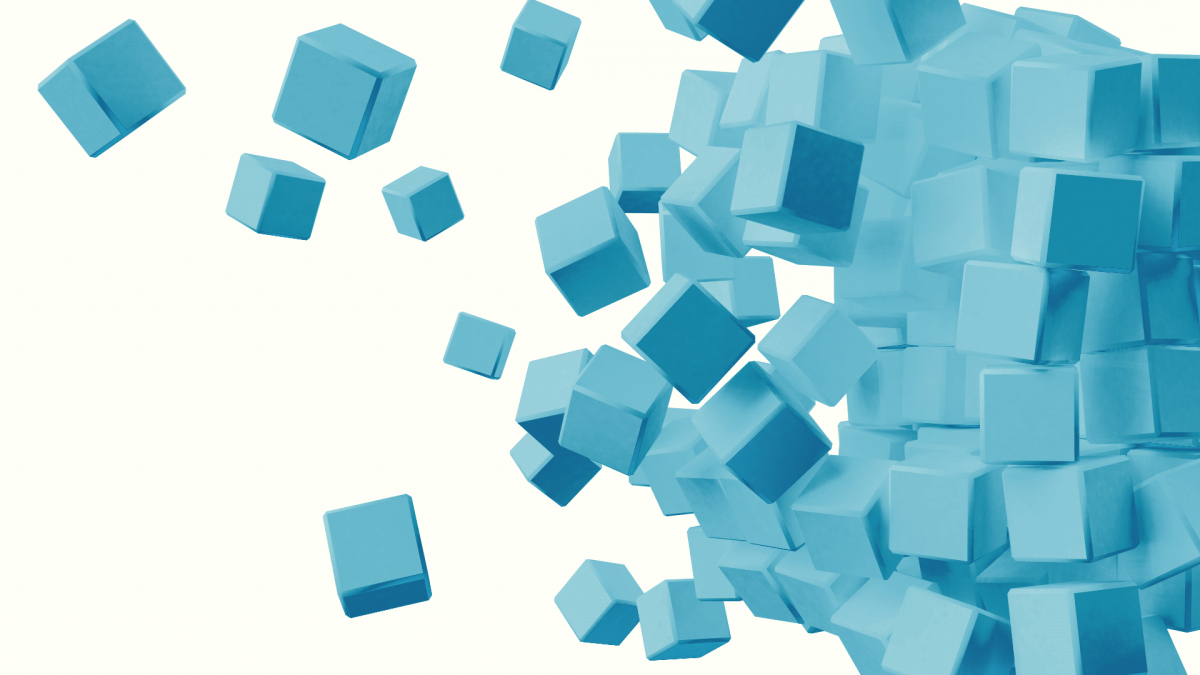ミスアンダースタンディング・ダンシング 12
とにかく実際に起きた現実だけをちゃんと受け止めようとした結果、それでもやはり私のキャパシティを大きく越えていたらしい。よほど変な顔をしていたようで、「ちょっと今日は家で寝といたら?」と母に心配され、その日は学校を休むことになった。熱を計ってみると実際に微熱が出ている。情けないなと思った。
ベッドに横になると思ったよりもすぐに眠気がやってくる。寝ている間に思考が整理されるっていうの、あんまり信じてないけど、今日はそうであればいいなと思いながらぼんやりした意識の中へ落ちていった。
意識が落ちていたのは一瞬だった気がするのに、次に起きるともう昼を過ぎていた。数日振りのよく寝た感覚。スカッと抜けるように晴れた空が気持ちいい。寝る前のお祈りが通じたのか、不思議と頭もすっきりしているようだった。
スマホに来ているメッセージにもそもそと返信を返していく。上から順番にメッセージを確認して、数件目に二郎くんからのメッセージがあった。今日は休んでいることを伝えると、すぐに既読がつく。続いてぽぽんと『大丈夫?』『おみまい行きたい』、少し間が空いて『ごめん今のなし』のメッセージがきた。打つの速いなあ。ありがとう、明日は登校するので大丈夫です、そう返しながら、明日のことを考える。やるぞ。ささやかでひそやかだけれど、私は一人気合いを入れた。
翌日は体温も平熱に戻っていて体調も良好だったので、予定通り登校することができた。初めて自分からメッセージを送って、今日は二郎くんと一緒に帰ることになっている。自分でやるぞと決めたこととはいえ、どうしても緊張はするものである。どこかそわついた気持ちで授業を受け、昼休み前に教室に戻っているときだった。
「**さん、ごめん。ちょっといいかな」
クラスメイトに呼び止められた。いつも明るくて社交的なあの子。二郎くんに差入れを断られたとき泣いていた、あの彼女だ。「うん」一緒にいた友だちに断って彼女のあとに続く。人気の少ない近くの廊下の端っこまでやって来ると、彼女はこちらに向き直った。
「あのさ、二郎くんのことなんだけど……。二郎くんと**さんって、付き合ってるの? 一緒に帰ってるの、見たって子がいて……」
ゆっくり、ひとつ呼吸をした。それからしっかりと彼女の目を見る。
「うん。付き合ってるの」
「…………そっか。そう、なんだ……。ごめんね、わざわざ呼び止めて、プライベートなこと聞いちゃって」
「う、ううん」
「教えてくれて、ありがと。それじゃっ」
言い終える前に彼女は踵を返して行ってしまった。偉いな、と思う。彼女はきっと本当に二郎くんのことが好きで、その気持ちと自分の気持ちにきちんと向き合ったのだ。思い返してみれば、二郎くんもずっと私のことを大事にしようとしてくれていた気がする。言葉が足りなくて齟齬が生まれてしまったけれど、彼なりの優しさをたくさん私に向けてくれていた。
私だけだ。私だけが、誰とも向き合わず一人でただビクビク縮こまって逃げようとしていた。そのくせ自分自身の気持ちすら曖昧なままにしてうろたえていたのだから世話がない。私も、彼らに恥ずかしくない人間になりたい。
放課後、緊張しながら特別教室棟の最上階に向かう。帰る前に少し話をさせてほしいと、二郎くんを呼び出したのだ。二郎くんに付き合えと言われたあの場所である。階段を上りきるとそこにはすでに二郎くんがいた。急いで来たつもりだけれど待たせてしまって申し訳なかったなと思いながら声をかける。彼は「おう」と短く返事をし、手にしていたスマホをポケットに仕舞った。
「ごめんなさい、呼び出したりして」
「それは、別にいーけど……。話ってなに?」
ちゃんと言うんだと覚悟を決めてここにいるはずなのに、いざ目の前にすると言いたいことがなかなか言葉にならない。うるさい心臓の音を一度シャットアウトするために深呼吸をした。そして意を決して口を開く。
「わ、私、二郎くんに謝らなくちゃいけないことがあって……。ごめんなさい!」
「えっ」
虚を突かれたような顔をした二郎くんは少しの間固まっていたけれど、「やだ、別れたくない」すぐにそう言って掴みかからんばかりの勢いで距離を詰めてきた。
「キスしようとしたの、ビビらしたんだったらごめん。〇〇がしたいって言ってくれるまでもうあんなことしねえから。他にもなんか嫌なことあるんだったら直すし、なあヤダよ。俺、〇〇と別れたくない……!」
「あっちが、違います! そういう話じゃなくて……!」
「……ちげーの?」
こくこくと必死に頷くと、途端に彼の肩から力が抜けていくのが見てとれた。「焦った~……」胸を押さえて大きく息をついている。
「えっと……、じゃあ、なんだ? 〇〇が謝るようなことってなんもなさそうだけど」
「それが、あの……。昨日二郎くんに好きって言われるまで、私、ちゃんと付き合ってると思ってなくて……。ごめんなさいっ」
「付き合ってると思ってなかったって……、え、誰と誰が?」
「二郎くんと、私が……」
「は……はあぁ〜〜〜〜!?」
心底信じられないとでもいうように大きな声をあげた二郎くんは、しかしすぐにハッとした顔になって、今度こそガシッと私の両肩を掴んだ。
「どっ……どういうことだよ!? だって俺、あんとき付き合ってくれって言って、そんで〇〇もハイって言ってくれたじゃん! それで付き合ってねえとか、そんなの……おかしいだろ!」
「ごめんなさい〜……っ! あの、そのときは二郎くんのこと全然知らなくって……、話したのも初めてだったし、いきなり告白されてびっくりしてたっていうか……。正直なことを言うと、その……、か、カツアゲの口実みたいなものだとばっかり思ってました……。本当にごめんなさい……」
「はあぁッ……? マジかよ……。なんでそんな……」
がっくりと肩を落とす二郎くんに、ひどく申し訳ない気持ちになる。ショックで当たり前だ。自分の気持ちを信じてもらえていなかったとなるとそれだけでキツいのに、さらにそれが好きな相手にとなるときっとダメージも数倍というものだろう。自分の言動を恥じながら、どうして事ここに至るまで二郎くんを信じられなかったのだろうと思う。どうして……。
「……好きって、昨日初めて聞いたから……?」
「へっ?」
「二郎くんと初対面だし、ちょっと、怖い人なのかなって思ってたし……、付き合ってって言われたけど二郎くんが私のことどう思ってるのか全然分からなかったから、それで……」
「……え、俺、好きって言って……なかったっけ……?」
うん、と声に出さず頷く。二郎くんは「うっ、マジか……」と小さく呟き片手で口を覆って黙ってしまった。眉間に皺が寄っているけれど、以前のように怖くはない。二郎くんのことを好きになったからという分かりやすい贔屓目もあるだろう。それにくわえて、彼はきちんと私のことを考えてくれていると今はもう知っているから。知らない彼の噂に震えるよりも、本当はもっと早くこうして目の前の二郎くんを見るべきだった。
ふっと小さく息をついて、二郎くんは「あー……」と意味のない声をもらす。それからぐっと背筋を伸ばした。
「俺が自分の気持ちをちゃんと言ってなかったせいで、勘違いさせちまって変な感じになったと……思う。ごめん。昨日言ったし知ってると思うけど、改めて、ちゃんと言うな。俺は、〇〇が好きだ」
真剣な瞳にまっすぐ見つめられて心臓が一際跳ね上がる。頬が熱い。二郎くんは私に対して真摯であろうとしてくれている。私もそれに応えなければ。
「けど、あんとき告白するまで〇〇と話したことなかったってのは、そうだからさ。仕切り直し! もっと俺のこと知ってもらえるようにがんばるから。それで〇〇も俺のこと好きってなってもらえたら、そのときもう一回告白する」
「……んっ?」
「うっし! そうと決まれば、〇〇に俺のこと好きになってもらえるようにどんどんアピールしてかねえとな! 帰ろうぜ、送ってく」
「えっ、あっ、ハイ」
今までのむっつりとした顔が嘘みたいに晴れた笑顔の二郎くんに促され、階段を降りる。あれっ、今、付き合う流れと別の方向に行ってしまった……よね? 「あの、二郎くん」「んー?」呼び止めようとしてみるけれど、ふっと微笑まれてなにも言えなくなってしまった。ウッ、眩しい……! 惚れた弱みもあるし、単純にめちゃくちゃ顔がいい。二郎くんにきゃあきゃあ言ってる人たちは私とは別世界の人と思っていたのに、今はその気持ちがよく分かる。この人が私に笑みを向けてくれているというだけで、なにもかも全部に敗北しましたというような気分になる。
そうして、帰りの電車にまで一緒に乗り、初めて二郎くんに家の最寄りのコンビニまで送ってもらった。いつもより饒舌に色んな話題を出してくれる二郎くんは、きっとお互いのことをもっと知ろうとしてくれている。彼の気持ちに応えよう、自分の気持ちをちゃんと伝えよう。そう思っていたはずなのに、二郎くんの眩しさに当てられているうちにコンビニに辿り着いてしまい、結局それ以上なにも伝えることができなかった。
「じゃあ、気を付けてな。なんかあったら連絡くれよ」
私というやつは、どうしてこうも腰砕けなのだろうか。
2023/08/29 初公開