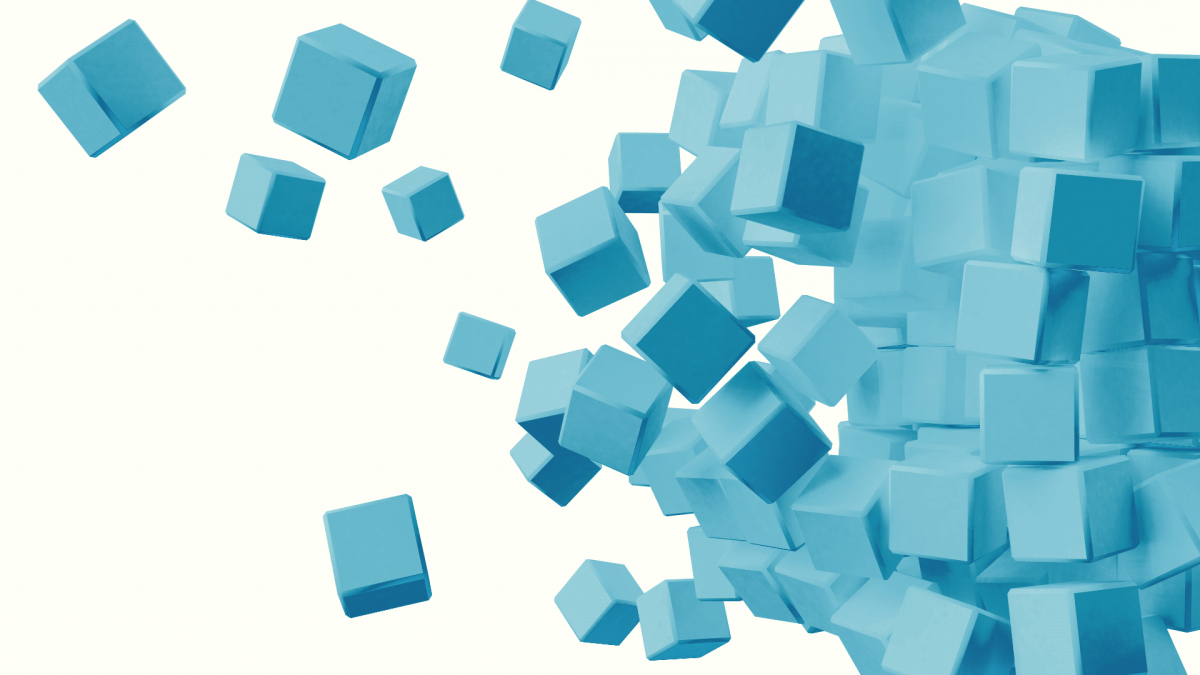ミスアンダースタンディング・ダンシング 13
その週はそれから二郎くんと一緒に帰ることができなかった。萬屋ヤマダの仕事が立て込んでいるらしく、その手伝いで忙しくしているのだという。普段顔を会わせる機会といったら下校時だけだったから、途端に接点がメッセージしかなくなってしまった。それでも、二郎くんは忙しい合間を縫って以前よりもこまめにメッセージをくれている。アピールすると言っていた割に内容は他愛のないもので、ときどき画像やリンクと一緒に「こういうの好き?」といった軽い質問が送られてくる程度だ。多分、私が気にしないように配慮してくれている。気の遣い方が上手い人なんだな。一度のやり取りは短くても、こうして二郎くんの新たな一面を知るたびに、彼のことを好きだという気持ちがどんどん膨らんでいく。
そう、端的に言ってドキドキしてしまっていた。私はちゃんと二郎くんに好きだと伝えていないのにだ。二郎くんだって、相手の気持ちが分からないまま顔を合わせられなくなるより、恋人だと関係をはっきりさせていた方が心情的に楽だったんじゃないだろうかと思う。両思いだということを私だけが知っている状況は、ひどくアンフェアだし二郎くんに対して不誠実なように感じられた。次に会うときにはちゃんと言おう。そう思っているけれど、二郎くんの忙しさを口実にして、勇気を出すべき場面を先延ばしにしているのは自分でも気付いていた。
土曜日、陽もほとんど落ちかけた夕方。今日は一日中机に向かっていたからそろそろ肩が凝ってきた。気分転換がてらにコンビニにでも行こうかな。充電器に繋ぎっぱなしにしていたスマホに手を伸ばしたちょうどそのとき、画面が明るくなってメッセージの通知が表示された。二郎くんからだった。
『今コンビニの近くまで来てるんだけど会えない?』
『できたらでいいんだけど』
あまりのできたタイミングに、思わずビクッと肩が跳ねた。一瞬ひるんでしまうけれど、いや、ここで尻込みしているようでは駄目だ。二郎くんが素直に気持ちを伝えてくれているのに、私はウダウダと迷っているばかりで何も返せていない。『今から行きます』『少し待ってください』急いで返信して、自分の恰好を見直す。そこのコンビニ行くだけだったらまあいいかなの服で、二郎くんにこれで会うのはちょっと流石に。吟味してる暇なんて無いから多少はマシな服に急いで腕を通し、大雑把に髪を整える。そこまで変、ではないはず。リップだけ塗って、もうこれでいいやとサンダルをつっかけて家を出た。
コンビニまで行くとすぐに入口の前にいる二郎くんの姿を見つけることができた。ラッシュガードを着たスポーティな出で立ちで、大きなリュックを背負っている。私に気付いた二郎くんの表情がパッと明るくなる。
「〇〇! 急に呼び出してごめんな。助っ人で呼ばれたのが近くだったから、〇〇の顔見れたらと思って」
「…………!」
反対に私の顔は引きつったものになっていたと思う。二郎くんの片頬には大きな湿布が貼ってあった。口の端も切れているようで、他にもところどころ青紫のあざができている。こんなに分かりやすい箇所を派手に怪我している人を初めて間近で見たので、私はひどく動揺していた。
「……やっぱ、いきなり呼び出すの、迷惑だったか?」
「や、そう……じゃなくて……。ど、どうしたんですか、その顔。助っ人ってことは、スポーツで……?」
「あ~……。これは、今日のじゃなくてその……、ちょっと、喧嘩売られちまって……」
「喧嘩」
私がついギクリと体を固くしてしまったのに二郎くんは目敏く気付いたらしい。慌てた様子で「でも! 俺は手ェ出してねえから!」と言葉を続ける。
「うるせえ奴らに絡まれただけで! やり返してはねえし、デカい怪我もないから。〇〇の嫌がることはしたくねえもんな」
「えっ」
「前、喧嘩はヤダって言ってたろ? あー……、けどひょっとして、怪我したとこ見せんのも怖かったか……?」
雷に打たれたような気分だった。私のせいだ。私が、考えなしに「喧嘩は嫌だ」なんてぼんやりしたことを言ってしまったから。だから、二郎くんは喧嘩を売られても反撃せず、一方的に殴られるばかりになり、そしてこんなにひどい怪我をしてしまった。馬鹿みたいに浮かれていた頭が一瞬にして冷水に浸けられたみたいにザッと冷める。申し訳なさで、もう彼の顔をまともに見ることができなかった。
「ご……ごめんなさい…………」
「いや、〇〇が謝るような……。え!? 待っ、な、なんで泣くんだよ!? やっぱ怖かったか!? 俺そういう、デリカシー無くてごめん!」
「ちが……私が悪くて……」
堪えようとしたが、それは無理だった。ポロポロと涙が次から次へと溢れて、堰を切ったように流れ始めてしまった。突然泣き出した私を見て、二郎くんは慌てた様子でおろおろしている。そうしてリュックの中を探ったかと思うと、タオルを一枚取り出した。
「これ、今日使ってねえヤツだから、使って。バッグ入れてたから汗臭いかもはしんねーけど……。あ、それともコンビニでなんか買ってきた方がいいか……!?」
「ちが、違うんです、ごめんなさい……。ふ、うぅ゛〜……」
「な、泣くなって……! とりあえず場所移そうぜ、な?」
うろたえている二郎くんからありがたくタオルを受け取り涙を拭う。まだ涙が止まらない私はさぞ面倒くさいだろうに、彼は辛抱強く優しく対応してくれた。
近くの公園に移動して、ベンチに並んで腰掛る。歩いているうちに少し涙は落ち着いてきたけれど、口を開くとまた泣いてしまいそうで、私は何も話せずにいた。
「俺、その、会いたいって気持ちで先走っちまって……。泣かせるつもりなんか無かったんだけどさ、ほんとごめん」
「そ、んなことないです……。……私が、悪いんです。タオル、ありがとうございます……、洗って返しますから……」
「んなことは全然、気にしなくていーから」
涙を拭って、息を吐いて、呼吸を整える。ひどく子どもっぽい振る舞いをしてしまった恥ずかしさと自己嫌悪はある。けれど、今度こそ全部言わなくちゃ。今日のことだって私がちゃんと言葉を伝えられていれば、きっとこんなことは起きなかったのだ。勇気を出すと決めたのも何度目だろう。二郎くんの顔を見れるほどにはそれを持ち合わせていない自分にうんざりする。だけどその分、全部言葉にしよう。
「私、たしかに喧嘩は嫌です。今まで喧嘩なんて映画や小説の中だけの出来事だと思ってたし、実際に二郎くんの話を聞いてるだけでも怖いし」
「うん……、だよな……」
「でも、喧嘩は嫌ですけど、それよりもっと、二郎くんが怪我する方が嫌だ……」
「えっ」
二郎くんの方へ上半身を向けて頭を下げる。また目の奥から涙が滲んできた。関係ない。言うんだ。
「私が言ったことのせいで、二郎くんに怪我させてしまってごめんなさい。そんなことをしたのに、二郎くんのことが好きでごめんなさい……」
二郎くんの顔が見れるほどの強さは無かったけれど、ちゃんと謝罪の言葉を伝えることができた。好きって、勇気を出して、ちゃんと言えた。顔や体は熱いし頭はくらくらする。体中の血がぐるぐる激しく巡っているようだ。
しばらくそうしていて、それでも何も言わない二郎くんにだんだんと不安が募ってきた。恐る恐る顔を上げて様子を窺うと、彼は真っ赤な顔で私を見て固まっていた。
「待っ……、え、いま……」
「すっ、好きです。二郎くんのこと。あの、本当はこないだこれも全部言えてたらよかったんですけど」
「好き……っ! ……て、あの、俺が言ってるのと同じ意味、ってコトでいいん、だよな……? 〇〇に、カノジョになってほしいってコトなんだけど」
「ハイっ」
妙に勢いよく答えてしまった。今度こそ全部誤解の無いよう言わなくちゃという気持ちと、初めて感じる高揚感でなんだか前のめりになっている自覚はちょっとある。二郎くんは一度何か言おうとしたけれどそれを飲み込んで、きゅっと口を結んだまま地面に視線を落とした。
彼女になってほしいとは言ってくれたけれど、やっぱり、駄目かもしれない。だって二郎くんはこんなにひどい怪我をしたんだから。横顔だと顔を覆う湿布がことさらに大きく見えて痛々しい。
悪い方の考えばかりが浮かんでタオルを握り締める手に力がこもる。ほんの少しの間のはずなのに、沈黙がひどく長く感じられて痛いほどだ。どうしたらいいか分からなくなって、ただじっと彼の言葉を待っていた。
不意に、二郎くんが立ち上がる。私の正面へ立つ彼の表情は薄暗い中でもよく分かった。耳まで真っ赤で、瞳は熱情に溢れている。
「〇〇のことが、好きだ。俺と付き合ってください」
運動部の人がいつもそうしているやり方で、二郎くんは真っ直ぐに頭を下げた。慌てて私も立ち上がる。
「わっ、私でよければ、よろしくお願い、します……!」
同じように頭を下げると、バッと二郎くんが体を起こして、それから細く長い息を吐きながらその場へしゃがみ込む気配がした。頭を上げてその推測はどうやら確かだったらしいと目で理解する。な、なにかマズいことを言ってしまっただろうか。隣へ並んでしゃがんで「どうかしましたか……?」声を掛ける。
「……嬉しくて、鼻血出そう」
そこでようやく、二郎くんと今日会ってから初めて、私はちょっとだけ笑った。
2023/09/06 初公開
ひとまずここでおしまい! 読んでくださってありがとうございます!
書き下ろしを追加して同人誌にまとめる予定なので、よろしければそちらもよろしくお願いいたします