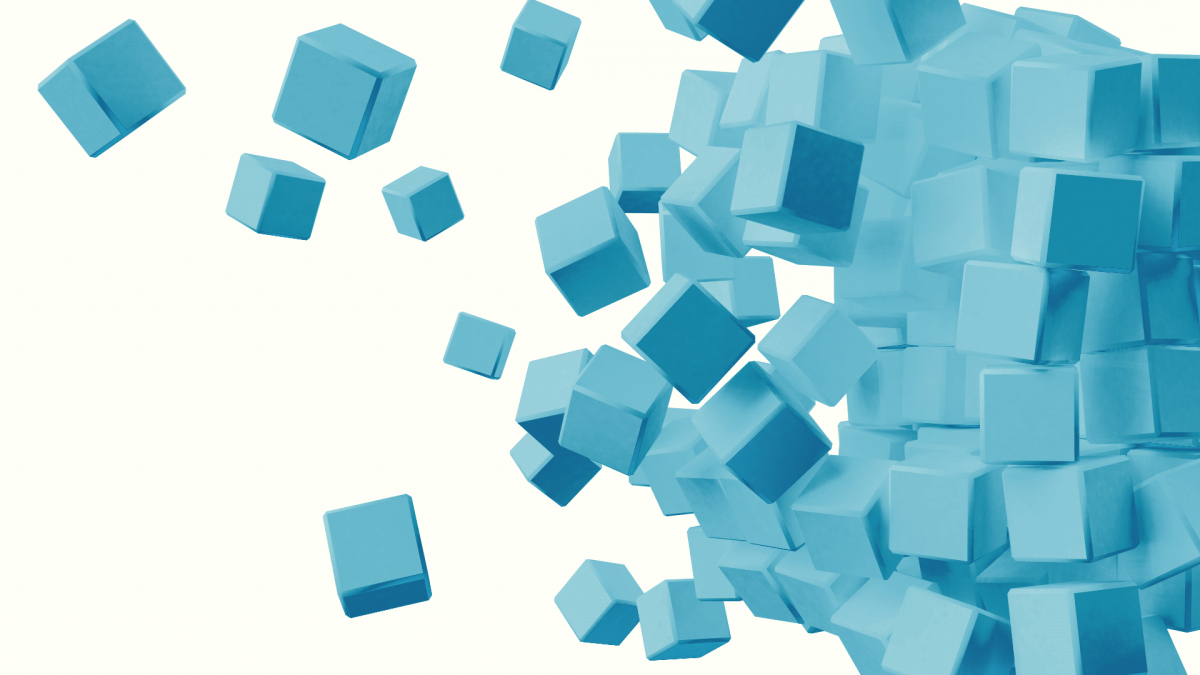ミスアンダースタンディング・ダンシング 10
満員電車に押されて今日も朝からちょっぴり疲れた。ここ数日上手く寝付けていないから余計に眠いし体がだるい。改札を抜けて、同じ制服の人の群れに混じっていく。今日は最初からハキハキ登校するような気分でもないけれど、前を行く二人の女子はそれにしたってのんびり歩いている。多分知らない子で、下級生だと思う。遅刻をするほどではないにしろ、さすがに自分の歩きやすいペースよりあんまりゆっくりなので足を速めて先に行ってしまうことにする。
「ホントだって! 昨日グループにめっちゃ回ってきたもん、三組のあの子がじろちゃんにコクったって」
「へ~。山田くん、彼女できたからってあんだけ言ってたのによくやるわぁ」
追い越す瞬間に彼女たちの会話が聞こえてしまった。内臓を撫でられたみたいにギクリとしてしまう。けれど、立ち止まるわけにはいかない。振り払うように歩く速度を上げる。
昨日は、山田二郎くんからのメッセージはなかった。今までだってメッセージが無かったことはある。だけどそういえば、昨日の放課後は用事があるから一緒には帰れないとも言っていた。もしかして、用事って、同級生の子に告白されることだったのかな。山田二郎くんはその告白を承諾したんだろうか。私にわざわざ声をかけたのは、きっと単に言うことを聞かせやすいからにすぎない。だから、山田二郎くんが付き合いたいと本当に思う子が現れたら、私なんてすぐにお役御免だ。
「…………っ」
そう思うとひどく胸がじくじくとした。山田二郎くんが誰か知らない女の子と歩いているところを想像するだけで、小石を飲み込んだみたいに息が苦しくなる。胸の中、自分でも知らない部分をなぞられるような不快感。
もう認めるしかないんだろう。もしこの感情が恋であればとか、彼のことを好きだとするととか、そんな仮定、そういう気持ちが無視できないくらい大きくならなきゃ出てこないに決まっている。最初に付き合えと言われたときには考えもしなかったのがいい証拠じゃないか。観念する。私は、二郎くんのことが好きなのだ。
「おはよ……、うわ、〇〇どしたの」
「……ねぶそく」
自分の気持ちを認めたからといって急に何かが変わるわけでもない。二郎くんは変わらず人気者だし、昨日告白をされたらしいという事実だって変えられやしない。いっそメッセージででもいいから、「別の子と付き合うことになったから」なんてサクッとフラれてしまった方がマシなんじゃないかとさえ思う始末だ。恋しているときが一番楽しいと歌っていたあの曲はフィクションに違いない。変な悪あがきをやめた分の余裕ができたとはいえ、初めて恋愛的な意味で人を好きになった私は、まだこの感情に振り回される一方である。
今日もどこか上の空のまま一日を過ごし、授業の内容もろくに頭に入らないまま放課後になってしまった。二郎くんからの連絡は無いから、その辺は気にせず過ごしてしまっていいはずだ。帰るにしてももう少し気力を回復してからにしたい。図書室にでも寄っていこうといつもの廊下を歩いていると、はたと人影に気付いた。二郎くんである。ここは彼に最初に話しかけられた場所だということにも同時に思い至った。また急に頭の中がぐちゃぐちゃになって、ドクドクと血の巡る音が耳の後ろで大きくなる。「あ」彼の方も私に気付いたようで、ぱちっと目が合った。せめて愛想よくしようと微笑んではみたけれど、絶対にぎこちないものになっていただろう。彼は少しの間逡巡してから、こちらに歩み寄ってきた。どうしよう。視線の置き場が分からない。
「悪い。ガッコで話しかけられんの嫌だと思うけど、直接言いたくて」
その言い方で、次になにを言われるのかおおよそ察してしまった。思わず身体が強張ってしまう。じりじり暑い夏の気温が嘘みたいに指先が冷たくなっていくような気がする。分かっていると思っていたくせに、いざ直接突きつけられそうになると恐ろしくてたまらなくなった。傷付きたくない。私の打算的な部分がそう訴えて、ぐるぐる必死に思考回路を動かす。だけどそれは二郎くんと向き合っているせいか、上手く働いてくれやしない。
「き、聞きました……。二郎くんが、同級生の子に告白されたって」
「ああ……。そっ、か、聞いたんだ……。それは、うん。昨日、呼び出されてさ」
彼の声はいつもよりもずっと小さくて、普段の彼からは想像もつかないほど気まずそうなものだった。涙が涙腺ギリギリまで上がってきているのが分かる。この先の言葉を聞きたくない。強く強くそう思った。
「でも、ちゃんと……、あっ!? おい!」
馬鹿。臆病。意気地なし。対話ができない卑怯者。頭の中で己をそう罵りながら、私はその場から走って逃げだした。
2023/08/22 初公開