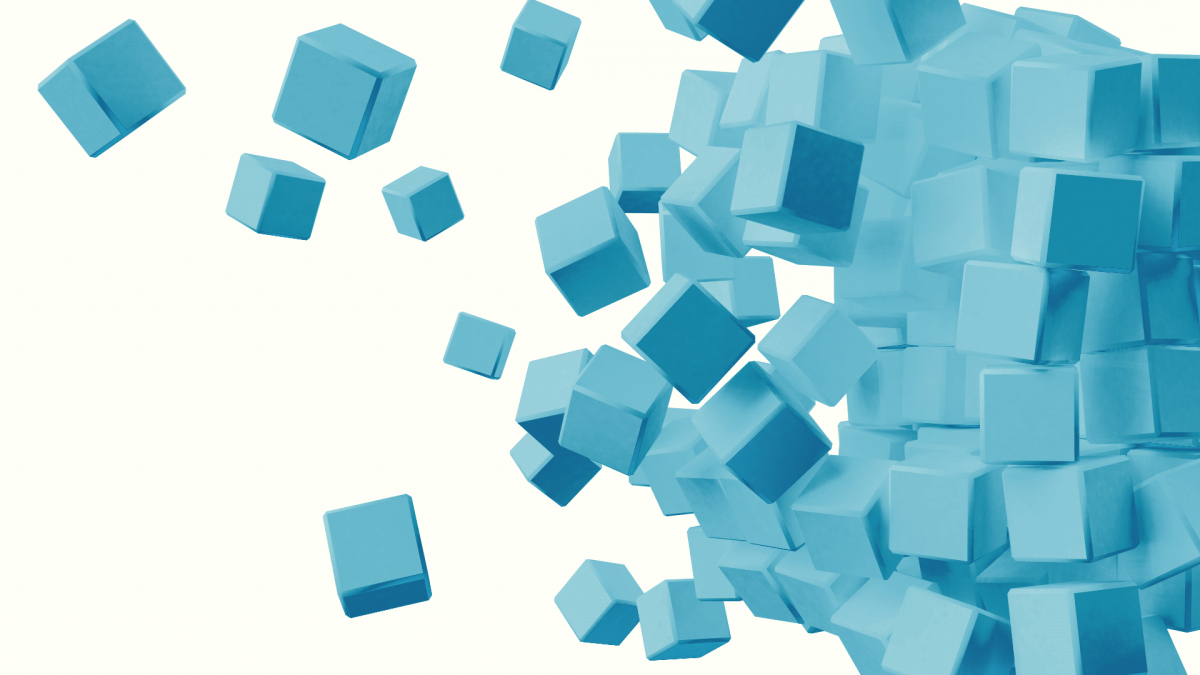ミスアンダースタンディング・ダンシング 09
一瞬の気の迷いだと思おうとしてみても、一度意識してしまった気持ちはなかなか消えてくれないものらしかった。寝れば忘れるとも思っていたのに、今までのこと、特に昨日二人で出かけたことが頭の中でぐるぐると回り続けている。丸一日勉強の日にするはずが、これっぽちも捗らなくて一日中ぼんやり過ごしてしまった。ろくに進んでいないノートにため息が出る。どうしようもない。
翌日の学校でも、山田二郎くんのことをなんとか振り払おうと努めた。だけど授業中でも友だちと話していても、ふとした瞬間に彼のことを思い出してしまう。今まで恋愛なんて縁遠いものだと思っていたから、これが本当に恋なのかどうかすらちょっと疑わしい気持ちもまだある。コイバナをしてる人たちって、もっときゃいきゃいと楽しそうにしていたような気がするのに。なにかにつけて相手のことばかり浮かんでしまって、なにをするにも上の空で頭の中がグチャグチャで、もう考えたくないのにそれでも勝手に思い悩んでしまう、こんな状況のことをみんなは楽しく感じているんだろうか? それとも私が慣れていないだけで、こういう状態こそが一般的な恋愛というもので、世間一般には現状は楽しい状態に入るんだろうか。分からない。なにもかも……。
「……〇〇ってば。ねぇ」
「へっ? ……ぅあ、ごめん。ボーっとしてた……」
「あ、やっぱり聞いてなかった? いいけどさ」
今日は友だちと一緒に放課後勉強しようとファミレスに来ていた。山田二郎くんの方もなにやら用事があるらしい。毎日一緒に帰っているわけではないし単に偶然こうなったのだけど、彼と一緒に帰らずにすんで助かったと思ってしまう。どんな顔をしたらいいのかどころか、今までどんな顔をして彼と会っていたかさえ思い出せなくなってきていた。
「やっぱさあ、今日の〇〇ヘンじゃない? なーんかあったでしょ」
「あっ……た、けどぉ……」
唇を尖らせてそう言うと彼女は私の方へ身を乗り出してくる。純粋に心配してくれていると分かる。だけど、私の方が今自分の置かれている状況をうまく言語化できる気がしない。自分の感情のことが自分でもまだよく分かっていない状態なのだ。彼女は信頼できる友だちである。できることなら相談したい気持ちはあれど、どう話したらいいものか分からない。
「まだ上手く説明できる気がしなくて……。でも話せるようになったら、ちゃんと話すから。ごめんね」
「う〜ん……。確かに〇〇は人に相談するのあんま得意じゃないもんねぇ。わかった。けど、なんかヤバそうだったらすぐ言ってよね! 話はいつでも聞くから!」
「うん、ありがとう〜……」
いつだって相談に乗ってくれる人がいるんだと思うだけでとても心強い。持つべきものは友である。昨日からずっとゴチャゴチャしていた頭が少しだけスッキリ晴れた気分だ。
「ごめん、それでなんの話だったんだっけ」
「うん、なんか昨日か一昨日かにに山田くんが彼女とデートしてるっぽい? とこを誰かが見たらしくて、また一部女子が大変そうだったね〜って話」
「へァ゛」
思わず変な声が出た。今一番聞きたくなかった話題と言っても過言では無い。恐ろしい発言をした張本人は私の奇声を気にした様子もなく、「人気者に恋した人は大変だよねぇ」なんてドリンクのストローをいじっている。
もし昨日のことだったら違うかもしれない。でも、土曜のことなら、山田二郎くんとデートしていた彼女というのはきっと私のことだろう。別に隠れようとはしていなかったから誰かに見られていてもおかしくないのだけれど。今まで一緒に帰っててこんな話が出てこなかったのが奇跡のようなものなんだけれど。しかし実際に見られていたらしいと分かると、なんというか、こう、途端に恥ずかしいようないたたまれないような気分でいっぱいになる。
「えっ、誰……、どのへんの人が見てたのかな……」
「え〜、一年の子から回ってきたらしいけどそこまでは? 私らの耳にも入るってことは結構広まってそうだけど、めちゃくちゃ目撃されたってワケではないんじゃない?」
「そ、そっかぁ……。でも噂広がってるってことは、確かに、……あ、荒れてそうだね……」
「そうそう。ガチ恋勢、多かったもんね」
「じゃあこれから……彼女の人の身元を探ったりとか……、山田くんと付き合ってるなんてどういうことって問いただしに行ったりとか……」
「いや流石にそこまではしないでしょ。マンガじゃないんだから」
しない、だろうか……。私の今の状態が山田二郎くんに恋してるからだとすると、好きな人ができるとこんなにも頭の中がこんがらがってしまうものらしい。であれば、普段は理性的な人だって感情的になって暴走してしまうこともあり得るのではないだろうか。見た人がこの学校にいるなら私の顔にいつたどり着いてもおかしくない訳で……。どんどん悪い想像をしてしまってビクビク縮こまる私を、友だちは「心配いらないって」と軽く笑い飛ばす。
「ガチ恋の人であればあるほど、そんなことしたって山田くんにバレちゃったらもう終わりだって分かってるでしょ。わざわざ山田くんの好感度下げるような真似はしないって」
「そう……だよね、そうかも……」
「そー。万一やる人が出たとしても山田くんにバレないようにすっごいコッソリやるだろうから、私たちが気にしなきゃいけないほど大事になることはまず無いまず無い。今まで通り遠巻きに野次馬させてもらお」
万一の話を言われると気になるけれど、彼女の言う通りなんだろう。仮に私が誰かにどうこう言われたとして、山田二郎くんが気分を害したりするとはあまり思わない。だけど、山田二郎くんを好きな子たちが友だちの言うように考えてるとしたら、きっとなにか起こる確率は低い……はずだ。山田二郎くんが差し入れを断るようになってから、あんなにもきゃあきゃあ騒いでいた子たちの姿はずいぶん見なくなった。山田二郎くんからどう思われるかを気にしているのは確かなんだろう。
「にしても山田くんは女子がいつも集まってくるのにタジタジだったって話だし、彼女ができてからかなり楽になっただろうね~」
なんでもないように友だちは言って、そうしてノートの方に意識を戻した。私も素振りだけはノートの文字を目で追いながら、内心では別のことを考えていた。
やっぱり、山田二郎くんが私に付き合えと言ったのはそういう効果を求めてのことだと思う。もしかしたら彼は悪い人ではないのかもと思い始めていたものの、それもきっとすぐ逃げられたりヘンな噂を流されたりしないようにという打算が含まれてのことに違いない。デート商法、ロマンス詐欺、……そういう単語が頭に浮かんできてペンを握る手にぎゅっと力が入る。ひどい。あんな風に、本当にデートみたいにされたら、私みたいなやつはすぐ好きになってしまうに決まっているじゃないか。
あの日放課後呼び出されてから今まで、彼が私をどう思っているのかを私はまだ聞いたことがない。
2023/08/20 初公開